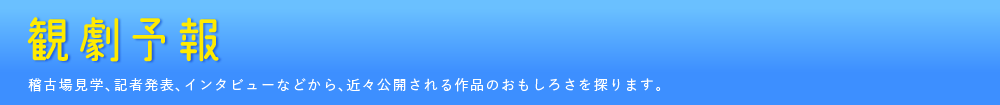生きていく日々に寄り添う珠玉のオリジナルミュージカル『いつか~one fine day』

人間ドラマを描き続ける韓国の映画監督イ・ユンギの最新作を原作に、ストレトートプレイからミュージカルまで幅広い作品を手掛ける板垣恭一の脚本・作詞・演出、新進気鋭の桑原まこの音楽による、オリジナルミュージカル『いつか~one fine day』が世田谷のシアタートラムで上演中だ(21日まで)。
『いつか~one fine day』は、2018年4月に東京芸術劇場シアターイーストで上演された『In This House~最後の夜、最初の 朝~』に続くconSeptのMusical Dramaシリーズ第2弾。妻に先立たれた男性と、昏睡状態の中で心だけ目覚めた目の見えない女性の奇跡の交流を通じて、誰の人生にも訪れる別れの絶望と、そこからの再生のドラマを生演奏と共に展開するオリジナルミュージカルとなっている。
【STORY】
保険調査員のテル(藤岡正明)は後輩タマキ(内海啓貴)の担当だった仕事を引き継ぐよう新任の上司クサナギ(小林タカ鹿)から命じられる。それは交通事故に遭い、昏睡状態に陥った盲目の女性エミ(皆本麻帆)から示談を勝ち取れというものだった。だが、エミの代理人マドカ(佃井皆美)には冷たくあしらわれ、彼女のソウルメイトだと名乗るトモ(荒田至法)からは罵られ、話を聞くこともままならず、テルは病室を追い出されてしまう。仕事が進まないなか、数か月前に亡くした愛妻マキ(入来茉里)のことをまだ整理できずにいるテルは酒に酔い、再びエミの病室を訪れる。そもそも目が不自由なエミが、なぜたった1人で事故現場にいたのか、持ち物にあったカセットテープには何が入っているのか。答えるはずのないエミに問いかけながら、テルはうっかり眠りこんでしまう。ところが翌朝、目覚めたテルの前に現われたのは、なんとベッドで眠り続けているはずのエミだった。
俄かには信じがたい出来事に混乱しながらも、自分にしか見えないエミと交流を重ねるテルは、いつしか事故の陰に消息不明のエミの母親サオリ(和田清香)の存在があることに気づいていき……。

和田清香 皆本麻帆
劇場に入ってまず目に入るのは、舞台の真ん中に位置する白いベッドと、舞台上に斜めに引かれた白いラインだ。物語は昏睡状態のままそのベッドで眠り続けているエミの病室を軸に、役者たちが動かすパーテーション、ソファー、椅子等によって、自在に変化する場面を重ねて進んでいく。テルにだけ見える元気に動いているエミ、テルの回想の中に、と単純には言えない形で現れる亡き妻のマキ、テルがいる現在に共に生きている人々。複雑に絡み合う現実と非現実、過去と現在、そしておそらくは死後の世界と現世。それらが白いラインの狭間で出会い、すれ違い、また交錯していく様に、演劇世界ならではの豊かさがある。
その物語に登場する8人の男女はそれぞれに異なる過去と、現在と、困難な悩みを抱えている。もちろん彼らの悩みには傍から見れば、そんなことに悩んでいるんだ~という若さが羨ましいものから、壮絶としか言いようのない大きさに絶句するものまで様々な色がある。けれども誰もが、それをこと改めて言い立てず、当たり前の顔をして日々を生きているのがとてもリアルだ。悩みのない人生などおそらくこの世にはないし、だからと言って誰もが「わたしは悲劇の主人公です」と泣きながら夕陽に向かって叫んではいない。それぞれの仕事や役割をこなし、できる範囲の楽しみも見つけて、日々コツコツと生きている。そんな今現在の日本の、日常にある、隣にいても不思議ではない人々が、作品の中に生きている。
そんな世界で語られるのが「ちゃんと死ぬ」というテーマだ。この世に生を受けたものはいつか必ず死を迎える。それは皆わかっているが、でも正直あまり真っ直ぐに見つめたいものではない。特に自分が迎える死以上に、愛する人が迎える死は、永遠にその時がこないようにとただ願うばかりのものに違いない。
だがこの作品は、そこにきちんと目を向けて、ちゃんと死ぬことは生き切ることだと伝えてくる。しかも去る側の想いと共に、見送る側の辛さや願い、愛するが故の懊悩に静かに寄り添ってくれる。その想いの深さ、とても悲しいのにとても温かい視点が、静かに胸に染みていく。

何よりも瞠目するのは、舞台が不思議なほどの明るさと、軽やかさを持っていることだ。転換の妙、思いがけない演者のリアクション、ダンス、そして多彩なミュージカルナンバーが、扱っているテーマの重さからは想像もつかないような笑いも随所に生み出していく。一方でおそらく台詞で説明されたら、奈落の底に落ちた気分になるだろうという告白が、ミュージカルナンバーの絶唱になることによって、歌い手の歌唱力に喝采を贈る気持ちが、良い意味で感情を昇華してくれるのも大きな力になっていた。改めて、一見ミュージカル向きとは思えないこの作品を、オリジナルミュージカルに仕上げた、脚本・作詞・演出の板垣恭一と作曲の桑原まこ、そしてそもそも企画を着想したプロデューサーの宋元燮の慧眼と、板垣が「社会派エンターテイメント」と呼ぶ世界観の目指すところ、その意義が感じられた。

藤岡正明
そんな作品の中で、テルを演じた藤岡正明の、確かな演技力と歌唱力が、作品に太い柱を通している。複雑に交錯する舞台にほぼ出ずっぱりの藤岡は、妻の死から立ち直れずにいるテルが、それでも生きなければならない日常を、実に細かい襞を感じさせて表現していく。どんなに絶望していても、人はふと笑う時もあれば、全く別の想いに思考が動くこともある。そうした揺れを含めたテルの変化が舞台の上に立ち上り、囁くようにも、どこまでも届くようにも歌える歌唱が想いを届けていく。役者本人にある一見やや強面な中に、びっくりするほど明るい笑顔が広がる持ち味もテル役に打ってつけで、クリエーターたちが目指す、いまの日本にあるべきオリジナルミュージカルの世界を体現した主演ぶりだった。

皆本麻帆 荒田至法
エミの皆本麻帆は、身体能力の高さと弾ける笑顔の眩しさと同時に、この人の中にあるファンタジー性、どこか妖精のような持ち味が、テルにだけ見えるエミの魂とも言える存在に真実味を与えている。光を知らずに生きて来たエミが、初めて見る世界、色の氾濫や情景を伝えるナンバーや、台詞の数々が、あまりにも当たり前になっていて気付かなかった世界を示し、こちらの目が開かれる想いがするのも、皆本の驚きや喜びをストレートに届ける力あってこそ。作品にとって欠かせない存在として、皆本の果たした功績は大きい。
そうした二人のみならず、出演者全員が役柄を鮮やかに描き出し、作品に群像劇としての魅力も与えたのが、更に舞台の味わいを深めている。

内海啓貴 佃井皆美
エミの代理人で親友のマドカの佃井皆美は、スラリとした長身と凜とした佇まいで、登場時からバッと目を引く存在感が力強い。心からエミを思っているからこそテルに敵愾心を向ける流れが自然で、そのマドカが次第にテルを受け入れていく描写の繊細さが際立ち、こんな親友が持てたエミは幸せだと思えたのが、作品の救いにもなっている。
エミの母サオリの和田清香は、26歳の娘を持つ女性を、ステロタイプなお母さん然として演じなかったのがまず当を得ていて、現代をきちんと感じさせる。何よりもこの人の圧巻と言うしかない歌唱力が、作品の「社会派エンターテイメント」を支えていて、この役柄を是非和田にと、板垣が熱烈にオファーしたという理由がストンとわかる歌唱と演技だった。
トモの荒田至法は、ゲイのストリートミュージシャンという原典の映画には登場しない役柄が、このオリジナルミュージカルに必要不可欠だったことを、見事に表して舞台に位置している。過剰にゲイを強調しない演じ方にも好感が持て、随所に笑いも取りつつ、エミのソウルメイトを自任するトモの心情を丁寧に表現していた。

入来茉里 藤岡正明
テルの妻マキの入来茉里は、この妻を失ったテルが現実を受け入れられないのももっともと思える、魅力にあふれる女性を、改めて振り返ると非常に短い「幸福な夫婦生活」の場面で的確に表出している。ここが押さえられていないと主人公が立たない重要な役割なだけに、入来のしなやかな美しさが貴重だった。
テルの上司クサナギの小林タカ鹿は、数字がすべての仕事人間をきちんと演じているからこそ、終盤に明かされるクサナギ自身のドラマが胸を打つ絶妙な芝居力が素晴らしい。長身で二枚目という完璧な外見の中に、どこかウイットのある持ち味も役柄に合っていて、クサナギという役柄により深みを与えていた。

小林タカ鹿 藤岡正明
テルの後輩タマキの内海啓貴は、子供の頃からなりたいと思っていた大人と、いま大人になった自分とのギャップに悩みながらも、生活水準は落としたくない、長いものに巻かれるしかないのか、と嘆息する若者像をチャーミングに演じている。所謂イマドキの若者だって、思うところはたくさんあるんだというタマキの悩みは眩しくも微笑ましく、作品の清涼剤としても良い効果になっていた。
何よりも彼ら8人が地に足をつけて生きる姿を応援したくなる、皆に幸福になって欲しい、そんな未来が「いつか」来て欲しいと願う心が、観ている側にも観た人の数だけあるはずの悩みや不安に、光の見える「いつか」がくることを信じさせてくれる。そんな力を届ける尊くも美しい作品が、日本のオリジナルミュージカルとして生まれ出たことを喜びたい。

【公演情報】
『いつか~one fine day』
原作◇映画『One Day』
脚本・作詞・演出◇板垣恭一
作曲・音楽監督◇桑原まこ
出演◇藤岡正明 皆本麻帆 佃井皆美 和田清香 荒田至法 入来茉里 小林タカ鹿 内海啓貴
●4/11~21◎シアタートラム
〈料金〉平日19時 7,500円 平日14時・土日 8,500円
〈お問い合わせ〉info@consept-s.com
〈公式サイト〉www.consept-s.com/itsuka
【取材・文/橘涼香 写真提供/conSept 】
【取材・文/橘涼香 写真提供/conSept】
Tweet