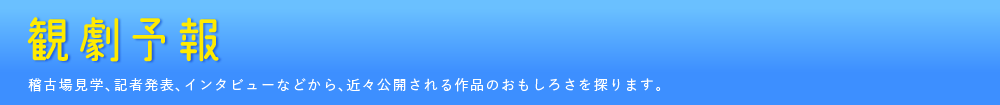帝国劇場から博多座までの旅路で進化を続ける『エリザベート』上演中!
 1996年に宝塚歌劇団により日本初演。2000年の東宝版初演から喝采を浴び続けてきた大ヒットミュージカル『エリザベート』が、2022年10月~11月の東京・帝国劇場公演、12月の愛知・御園座公演、12月~2023年1月の大阪・梅田芸術劇場メインホール公演を経て、1月11日から全国公演最終地福岡・博多座で上演中だ(31日まで)。
1996年に宝塚歌劇団により日本初演。2000年の東宝版初演から喝采を浴び続けてきた大ヒットミュージカル『エリザベート』が、2022年10月~11月の東京・帝国劇場公演、12月の愛知・御園座公演、12月~2023年1月の大阪・梅田芸術劇場メインホール公演を経て、1月11日から全国公演最終地福岡・博多座で上演中だ(31日まで)。
オーストリアハプスブルグ帝国の美貌の皇妃エリザベートの生涯を、自由を渇望して闘い続けた日々として描いたこの作品は、脚本・歌詞ミヒャエル・クンツェ、音楽・編曲シルヴェスター・リーヴァイの手によって、1992年にウィーンのアン・デア・ウィーン劇場で初演され、以来現在まで、ウィーン劇場協会製作によるミュージカル群最大のヒット作品であり、ドイツ語で書かれたミュージカルの金字塔の名を欲しいままにしている。ミュージカルと言えばブロードウェイとウエストエンド発の作品が世界の主流だった時代に、ある時はロックで、ある時はポップで、キャッチ―でありつつ陰影深い複雑なメロディーを持つ楽曲の魅力と、ヨーロッパ随一の美貌と讃えられ、放浪の皇妃とも呼ばれたエリザベートの謎多い人生に関わった人々だけでなく、「死」という概念を具現化して登場させた魅力的な劇構成が、「ウィーン発ミュージカル」を世界に知らしめ、魅了し続けているのだ。
そんな作品が、宝塚歌劇団での日本初演を経て、東宝版として初演されてから22年。本来なら東宝版20周年記念公演として、2020年に華々しく上演の予定だったが、瞬く間に世界を覆った新型コロナウィルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて、記念公演は無念にも幕を開けることが叶わず、今回一部キャストを入れ替えての仕切り直し公演が遂に実現したのだ。ただ、残念ながらコロナ禍は未だ終息したとは言い難く、今回の上演も東京・帝国劇場公演、愛知・御園座公演が、千穐楽を迎えられないまま幕を下ろさざるを得なかったり、キャストの変更、中止となる公演をいくつも数えるなど、様々な災禍に見舞われた。それでも尚、最終地福岡・博多座に駒を進めたカンパニーは、それぞれに力強さを増し、作品の中でハプスブルグ帝国が抱える大きな困難の数々が、ミュージカルのドラマティックな場面として昇華されていく様とあたかも呼応するかのように、観る者を魅了し、心をつかんで離さないこの作品にしかない魅力を逞しく増幅させている。
特にこの2022年~2023年の公演には、『エリザベート』というミュージカルで、トートが「愛と死の輪舞」を歌うことで抱えたパラドックスが、新たに山崎育三郎も加わったトート役者たちによって、そして、四半世紀以上この作品と共に歩んできた潤色・演出の小池修一郎によって、ついに克服されたと感じられた、非常に意義深いものになった。
パラドックスと言ったそもそもには、ウィーン発ミュージカル『エリザベート』が宝塚歌劇団で初演されたことからはじまった、日本版独特の色合いが起因している。厳格なスターシステムを敷く宝塚歌劇団には、主人公は男役トップスターでなければならないという命題があり、皇妃エリザベートをタイトルロールとするこの作品でも、その一線は固く守られ、エリザベートの「死」への渇望の具現化だったトート(死)は「黄泉の帝王トート閣下」として作品の主人公に押し上げられる。小池の周到な潤色は例えば「ミルク」の場面にもトートが登場するにはじまる、舞台に死の影が差す時には、必ずトートも存在しているという考え方からくる、こと細かい出番の増幅だけでなく、その根幹に人間が決して避けては通れない、誰もが必ず最後のダンスを踊ることになる「死」という絶対的な存在が、、宝塚版の為に書き下ろされた「生きたお前に愛されたいんだ」とエリザベートを求めるテーマ曲「愛と死の輪舞」を歌い上げることによって、自らその絶対的優位を手放してしまう究極の自己矛盾を生み出した。ここではただ時が過ぎるのを待っているだけでは、トートの思いは成就しない。

花總まり

愛希れいか
だが、それから4年。トートのオリジナルキャストだった一路真輝が真のタイトルロールとして、エリザベートを演じてはじまった東宝版初演でも、この「愛と死の輪舞」が残されたのはある意味予想外だった。主人公が原典通りにエリザベートその人になっても、この楽曲が同じ歌詞のまま位置したことによって、東宝版トートもまたそこからの長い年月、自己矛盾を抱えたまま作品に「黄泉の帝王」として君臨し続けることになる。東宝版でも引き続き演出を担った小池は、主たる登場人物たちの上手、下手の出入りを、宝塚版とは全て逆にするという、まず心血を注いだのは宝塚版との差異を如何にしてつけるかだったのだろう、としか思えないこと細かな変更と、宝塚版では極力排除していたエリザベートのエゴイスティックな面をむしろ強調することによって生じるリアリズムを追求しながら、トートを特異な立場に、言うなればもう1人の主人公として位置づけ続けた。ここに立ち向かえたのは、なんと言っても東宝版オリジナルキャストの山口祐一郎の存在あったればこそで、まさに帝王にふさわしいカリスマ性と、絶対的な歌声を持った山口が「愛と死の輪舞」を歌うトートのパラドックスを、自らのオーラでねじ伏せ、ある意味では見事に煙に巻いたことが大きかった。これによって東宝版トートは舞台上に君臨する黄泉の帝王たり得たし、芝居力の面白さで突出していた同じ東宝版初演のトート役内野聖陽をはじめ、トリックスター的な個性派武田真治。歌唱表現の幅に優れる石丸幹二。あまりに高いビジュアル力に目を瞠った城田優。あたかも野獣のようだったマテ・カマラスのいずれもが、各々の武器で自己矛盾を克服していった。
そして2015年、これまでも様々な演出変更を施してきた東宝版『エリザベート』は、ここでガラリと美術、演出を刷新。宝塚初演の、つまり日本で最初にエリザベート役を演じた花總まりが、再び東宝版でエリザベートを演じる。更に2000年の東宝版初演の皇太子ルドルフ役でミュージカル界に彗星の如くデビューして以来、大活躍を続けてミュージカルスターとしての地位を確かなものにしていた井上芳雄が、トート役として作品に帰ってくるという、大きな二つの話題と共に幕を開けた。その新たなミュージカル『エリザベート』から、確実に見えてきたものは、エリザベートの自由を求める魂は、遂にトートの愛からも逃げきったのだという感触だった。それは「最後の接吻」のあとで、自分の腕のなかで物言わぬ躯となったエリザベートを棺に横たえる際の、井上トートのあまりにも複雑な表情が示唆したものだったが、そのことがよりわかりやすく、言うならば誰の目にも明白になったのが、今回2022年~2023年の公演だった。
ひとつには小池修一郎その人が、『エリザベート』東宝初演からの22年間で、宝塚で上演した作品を東宝や、梅田芸術劇場製作として新たに上演する機会を多く重ね、前述したような「両者を変えなければならない」と、少なくとも観客側からは意識しているように見えた時代の力みが抜け、あくまでも作品を違うカンパニーで届けるだけという、ナチュラルな地点に達したことがあると思う。特に今回は自分をエリザベートだと思い込んでいる精神を患ったヴィンディッシュの造形に宿る鋭さや、マダム・ヴォルフが女主人を勤める娼館の描写が持っていた色濃さが全体にやや中和されていて、もちろん宝塚とは異なるが、東宝版としての美と退廃に注力しているのが大きな変化に感じられた。
もうひとつには、ここ数年で一気に強く意識されるようになった多様性の尊重や、性差による美徳の違いの打破を強く志向する機運が、エリザベートがトートに完全勝利することに、一切の忖度を必要としない土壌を作り上げたことがある。世界で戦闘が続き、暗い時代に転がり落ちていっているのを感じずにはいられない現代の、この空気のなかで、自由の前には死さえ恐れるに足りない存在だと、皇妃が高らかに宣言することにこそカタルシスが生まれる。これは東宝初演からの22年間で、ミュージカル『エリザベート』がたどりついたひとつの境地だった。こんなにもエンターティメントでありつつ、こんなにも時代を写す鏡でもある。そこに、この作品の持つ底知れない力を感じずにはいられない。
 そんな2022年~2023年の上演のなかで、日本初演の『エリザベート』タイトルロールのオリジナルキャストであり、読売演劇大賞優秀女優賞、菊田一夫演劇賞大賞、更に2019年にはオーストリア共和国有功栄誉金章も受章するなど、四半世紀を超える表現者としてのキャリアのなかで、エリザベートと共に歩んだ花總まりは、この公演をエリザベート役の集大成と位置付けていて、オーストリア皇后となり、更に放浪を続ける晩年に円熟味を深めている。少女時代との身体表現の差異が大きいからこそ、狂気にも似た魂のさすらいが胸を打ち、それは博多座公演で更に濃い陰影となっていた。ドレス姿の美しさも盤石で、当代の姫役者と謳われる人だけに、まだまだエリザベートを演じられるだろうと思えるが、だからこそここを区切りと考えるのが、花總本人の美学なのかもしれない。東京・帝国劇場での初日開幕コメントで「花總まりが演じる“エリザベート”がどんなエリザベートであったかは、ご覧になったお客様が決めることだと思います」と語っていたその旅路のたどり着く先を、博多座だけではなくライブ配信によって多くの人が観る機会を得られることは何よりの配慮で、進化し続ける花總のエリザベート像を見届けたい。
そんな2022年~2023年の上演のなかで、日本初演の『エリザベート』タイトルロールのオリジナルキャストであり、読売演劇大賞優秀女優賞、菊田一夫演劇賞大賞、更に2019年にはオーストリア共和国有功栄誉金章も受章するなど、四半世紀を超える表現者としてのキャリアのなかで、エリザベートと共に歩んだ花總まりは、この公演をエリザベート役の集大成と位置付けていて、オーストリア皇后となり、更に放浪を続ける晩年に円熟味を深めている。少女時代との身体表現の差異が大きいからこそ、狂気にも似た魂のさすらいが胸を打ち、それは博多座公演で更に濃い陰影となっていた。ドレス姿の美しさも盤石で、当代の姫役者と謳われる人だけに、まだまだエリザベートを演じられるだろうと思えるが、だからこそここを区切りと考えるのが、花總本人の美学なのかもしれない。東京・帝国劇場での初日開幕コメントで「花總まりが演じる“エリザベート”がどんなエリザベートであったかは、ご覧になったお客様が決めることだと思います」と語っていたその旅路のたどり着く先を、博多座だけではなくライブ配信によって多くの人が観る機会を得られることは何よりの配慮で、進化し続ける花總のエリザベート像を見届けたい。
 もう1人のエリザベートの愛希れいかは、宝塚歌劇団月組のトップ娘役としての集大成としてこの役を演じ、2019年から東宝版で同役を演じていて、歌唱の高音域の充実と共に、いまが伸び盛りの勢いを強く感じる。その昇り龍のような姿は帝国劇場公演から、最終地博多座公演までの4ヶ月の期間だけをとっても明白で、堂々たる深化に驚かされた。弾けるように溌剌とした少女時代から、エリザベートが求める自由は、例え物事が計画通り上手く運んで、姉が皇后になり彼女は今少し慣習や義務の少ない結婚をしていたとしても、決して得られなかったのではないか。そう想起させる愛希エリザベートの自由への希求の強さが眩しくもあり、どこか壮絶でもある。だからこそ自らトートに最後の接吻を求めていく姿に、この作品がエリザベートの勝利をもって見事に完結したことを実感させるし、その勝利が「死」であることに深いものが残った。
もう1人のエリザベートの愛希れいかは、宝塚歌劇団月組のトップ娘役としての集大成としてこの役を演じ、2019年から東宝版で同役を演じていて、歌唱の高音域の充実と共に、いまが伸び盛りの勢いを強く感じる。その昇り龍のような姿は帝国劇場公演から、最終地博多座公演までの4ヶ月の期間だけをとっても明白で、堂々たる深化に驚かされた。弾けるように溌剌とした少女時代から、エリザベートが求める自由は、例え物事が計画通り上手く運んで、姉が皇后になり彼女は今少し慣習や義務の少ない結婚をしていたとしても、決して得られなかったのではないか。そう想起させる愛希エリザベートの自由への希求の強さが眩しくもあり、どこか壮絶でもある。だからこそ自らトートに最後の接吻を求めていく姿に、この作品がエリザベートの勝利をもって見事に完結したことを実感させるし、その勝利が「死」であることに深いものが残った。
 東京・帝国劇場公演でトートとしてデビューを果たした山崎育三郎は、持ち前の歌唱力と独特のビジュアルで、ロックスターを感じさせて舞台に現れたのが鮮烈だった。これはオリジナル台本に「現代のポップスターのようなアンドロギュノスである」と書かれていたという、ウィーン初演が求めたトート像に近く、良い意味で強烈にナルシスティックだし、どこか爬虫類的な質感もあって面白い。トートダンサーを従えて登場する様からあたかも全体を司っている感覚があるのは、2015年から2019年の公演までルキーニ役を演じている経験も大きいだろう。髪の色を含めた髪型などビジュアルにも日増しに変化が見えていたので、帝国劇場公演のみの出演だった山崎の千穐楽が実現しなかったのは痛恨だが、Blu-rayとDVDとして映像化されるのは朗報で、壮絶なチケット難でその進化を見届けられなかった観客も多いことだろうから、映像の完成を楽しみにしている。
東京・帝国劇場公演でトートとしてデビューを果たした山崎育三郎は、持ち前の歌唱力と独特のビジュアルで、ロックスターを感じさせて舞台に現れたのが鮮烈だった。これはオリジナル台本に「現代のポップスターのようなアンドロギュノスである」と書かれていたという、ウィーン初演が求めたトート像に近く、良い意味で強烈にナルシスティックだし、どこか爬虫類的な質感もあって面白い。トートダンサーを従えて登場する様からあたかも全体を司っている感覚があるのは、2015年から2019年の公演までルキーニ役を演じている経験も大きいだろう。髪の色を含めた髪型などビジュアルにも日増しに変化が見えていたので、帝国劇場公演のみの出演だった山崎の千穐楽が実現しなかったのは痛恨だが、Blu-rayとDVDとして映像化されるのは朗報で、壮絶なチケット難でその進化を見届けられなかった観客も多いことだろうから、映像の完成を楽しみにしている。
 その山崎とダブルキャストで出た帝国劇場公演から、愛知・御園座公演、大阪・梅田芸術劇場メインホール公演をシングルキャストとして支え、更に最終地福岡・博多座でもトートを演じ続ける古川雄大は、2019年の初トートで見せた耽美な「この世のならぬ者」感から、喜怒哀楽の表現を前面に出した、言葉はそぐわないかもしれないがそれでも「人間的」と言いたいトートを表出してきたのが新鮮だった。エリザベートに恋焦がれていて、「死」としての俺様感を誇示しながらも、彼女に拒絶される度に傷を深めていく過程が鮮明で、こんなにも純粋に一喜一憂するトートを観たのは初めてだと感じた。だからこそ遂にエリザベートの愛を得たと狂喜した瞬間に、そのエリザベートを失う茫然自失の表情が忘れ難く、このあとトートは立ち直れるのだろうかと案じられたほど。孤高の「死」も楽々と演じられるビジュアルを持つ人が、こうしたトート像を描いて、2022年~23年のエリザベート完全勝利を象徴する存在になったのが、なんとも貴重だった。カウントの取り方に独自のスタイルがある歌唱にもますます余裕が出て、役柄の解釈の方向性によくあっている。映像化も、配信も古川トートの細かい表情変化を観るには打ってつけで、楽しみが広がる。
その山崎とダブルキャストで出た帝国劇場公演から、愛知・御園座公演、大阪・梅田芸術劇場メインホール公演をシングルキャストとして支え、更に最終地福岡・博多座でもトートを演じ続ける古川雄大は、2019年の初トートで見せた耽美な「この世のならぬ者」感から、喜怒哀楽の表現を前面に出した、言葉はそぐわないかもしれないがそれでも「人間的」と言いたいトートを表出してきたのが新鮮だった。エリザベートに恋焦がれていて、「死」としての俺様感を誇示しながらも、彼女に拒絶される度に傷を深めていく過程が鮮明で、こんなにも純粋に一喜一憂するトートを観たのは初めてだと感じた。だからこそ遂にエリザベートの愛を得たと狂喜した瞬間に、そのエリザベートを失う茫然自失の表情が忘れ難く、このあとトートは立ち直れるのだろうかと案じられたほど。孤高の「死」も楽々と演じられるビジュアルを持つ人が、こうしたトート像を描いて、2022年~23年のエリザベート完全勝利を象徴する存在になったのが、なんとも貴重だった。カウントの取り方に独自のスタイルがある歌唱にもますます余裕が出て、役柄の解釈の方向性によくあっている。映像化も、配信も古川トートの細かい表情変化を観るには打ってつけで、楽しみが広がる。
 そして、謂わば真打ち登場の体で福岡・博多座に降臨した井上芳雄は、「生きたお前に愛されたいんだ」と「死」である自分が願うことが、どんな結末を迎えるかをエリザベートとの出会いから既に知っていて、それでも彼女を求めずにはいられない自らの思いに一種の怒りも覚えていることが伝わってくるトート像を構築してきた。この己の愛に苛立つトートという存在もまた鮮烈で、終始「トート閣下はご機嫌斜め」だからこそ、より露悪的だったり、自虐的だったりする表現のひとつ一つに井上の個性が生きている。端的に言えば相当に拗れているトートなのだが、盤石の歌いっぷりとマント捌きを含めた舞台での存在感が大きいからこそ、こうした捻りある表現が黄泉の帝王のなかで成立しているのはやはり井上ならではだ。今回の『エリザベートが』現帝国劇場での最後の上演だったと伝え聞くと、誰が入れると言うのかは全くおいて、この作品の東宝初演がデビューだった井上にこそ、やはり例え数日でもいいから帝国劇場にも出演して欲しかったという思いも残るが、是非何年かのちにこけら落としを迎えるはずの新帝国劇場に作品をつなぐ役目を果たして欲しいし、博多座の雄姿が配信されることも嬉しい。
そして、謂わば真打ち登場の体で福岡・博多座に降臨した井上芳雄は、「生きたお前に愛されたいんだ」と「死」である自分が願うことが、どんな結末を迎えるかをエリザベートとの出会いから既に知っていて、それでも彼女を求めずにはいられない自らの思いに一種の怒りも覚えていることが伝わってくるトート像を構築してきた。この己の愛に苛立つトートという存在もまた鮮烈で、終始「トート閣下はご機嫌斜め」だからこそ、より露悪的だったり、自虐的だったりする表現のひとつ一つに井上の個性が生きている。端的に言えば相当に拗れているトートなのだが、盤石の歌いっぷりとマント捌きを含めた舞台での存在感が大きいからこそ、こうした捻りある表現が黄泉の帝王のなかで成立しているのはやはり井上ならではだ。今回の『エリザベートが』現帝国劇場での最後の上演だったと伝え聞くと、誰が入れると言うのかは全くおいて、この作品の東宝初演がデビューだった井上にこそ、やはり例え数日でもいいから帝国劇場にも出演して欲しかったという思いも残るが、是非何年かのちにこけら落としを迎えるはずの新帝国劇場に作品をつなぐ役目を果たして欲しいし、博多座の雄姿が配信されることも嬉しい。
 皇帝フランツ・ヨーゼフの田代万里生は、本来の持ち味である爽やかな二枚目の香りを若き皇帝時代に存分に振りまきつつ、近年果敢に取り組んでいるアクの強い役柄で広げた幅を、老境に差し掛かる皇帝の姿で遺憾なく発揮していて、全く臆することなく老いの表現に飛び込んでいる様に感嘆する。俳優田代万里生が重ねてきた経験が、フランツ・ヨーゼフの歩む人生そのものに生きていて、歌声にもそれが現れたのが頼もしい。
皇帝フランツ・ヨーゼフの田代万里生は、本来の持ち味である爽やかな二枚目の香りを若き皇帝時代に存分に振りまきつつ、近年果敢に取り組んでいるアクの強い役柄で広げた幅を、老境に差し掛かる皇帝の姿で遺憾なく発揮していて、全く臆することなく老いの表現に飛び込んでいる様に感嘆する。俳優田代万里生が重ねてきた経験が、フランツ・ヨーゼフの歩む人生そのものに生きていて、歌声にもそれが現れたのが頼もしい。
 もう1人のフランツ・ヨーゼフ佐藤隆紀は2015年公演以来のカムバックだが、その間に『レ・ミゼラブル』のジャン・バルジャン役を経ていることで深めた芝居面の充実が顕著に表れて心強い。初登場時はどこかぬいぐるみを思わせる愛らしさがありつつ「私の帝国内で諸民族は平等だ」と宣言する皇帝のまっすぐさ、真摯さが終始貫ぬかれていて、終盤に向けて悲哀が深まる歌唱で魅了する力にもやはり絶大なものがある。
もう1人のフランツ・ヨーゼフ佐藤隆紀は2015年公演以来のカムバックだが、その間に『レ・ミゼラブル』のジャン・バルジャン役を経ていることで深めた芝居面の充実が顕著に表れて心強い。初登場時はどこかぬいぐるみを思わせる愛らしさがありつつ「私の帝国内で諸民族は平等だ」と宣言する皇帝のまっすぐさ、真摯さが終始貫ぬかれていて、終盤に向けて悲哀が深まる歌唱で魅了する力にもやはり絶大なものがある。
 舞台全体が、この人が語る証言という形になっている大役のルイジ・ルキーニには初役が揃い、黒羽麻璃央は東宝ミュージカルに初登場。作品全体を掌で転がしているというこれまでのルキーニ像より、制御できない自身の感情をトートに操られていく一面も見えたのが、黒羽の演じるルキーニとして印象深い。証言が認められて、無罪放免になってもいいのでは?と思わせもするルキーニで、小池の潤色によく叶っている。
舞台全体が、この人が語る証言という形になっている大役のルイジ・ルキーニには初役が揃い、黒羽麻璃央は東宝ミュージカルに初登場。作品全体を掌で転がしているというこれまでのルキーニ像より、制御できない自身の感情をトートに操られていく一面も見えたのが、黒羽の演じるルキーニとして印象深い。証言が認められて、無罪放免になってもいいのでは?と思わせもするルキーニで、小池の潤色によく叶っている。
 一方、上山竜治のルキーニは、世間をあっと言わせることが全ての目的で、それを果たしたあとのいまは物語を傍観者的に再現している、という風情なのがこれもまた新たなルキーニ。『レ・ミゼラブル』のアンジョルラスのようなカリスマ的リーダーから、下世話な小物までと役幅が広い人らしく、場面によって見せる顔にも様々な変化があり、こちらは有罪だろうな、という着地点の違いを見比べる妙味の大きいダブルキャストだった。
一方、上山竜治のルキーニは、世間をあっと言わせることが全ての目的で、それを果たしたあとのいまは物語を傍観者的に再現している、という風情なのがこれもまた新たなルキーニ。『レ・ミゼラブル』のアンジョルラスのようなカリスマ的リーダーから、下世話な小物までと役幅が広い人らしく、場面によって見せる顔にも様々な変化があり、こちらは有罪だろうな、という着地点の違いを見比べる妙味の大きいダブルキャストだった。
 ミュージカル俳優としての登竜門とも呼ばれる皇太子ルドルフの二人も初役で、その1人甲斐翔真は帝国の皇太子として育ち、真剣に国を憂うからこそ皇帝たる父親と衝突していく王道のプリンスとして登場してきたのが、近年の『エリザベート』ではむしろ新鮮で、『ルドルフザ・ラスト・キス』の皇太子像を彷彿とさせる。斜陽に向かう帝国を立て直したい理想と、母のエリザベートとだけはわかり合えると、露ほども疑っていなかった思いを砕かれたあとの絶望のコントラストが強く、自ら死を選んだとも見えるのが今回の上演との親和性を高めた。なかでも井上とのビジュアルバランスや声質のハーモニーがよくあっていて、これは博多座だけの聞き物だった。
ミュージカル俳優としての登竜門とも呼ばれる皇太子ルドルフの二人も初役で、その1人甲斐翔真は帝国の皇太子として育ち、真剣に国を憂うからこそ皇帝たる父親と衝突していく王道のプリンスとして登場してきたのが、近年の『エリザベート』ではむしろ新鮮で、『ルドルフザ・ラスト・キス』の皇太子像を彷彿とさせる。斜陽に向かう帝国を立て直したい理想と、母のエリザベートとだけはわかり合えると、露ほども疑っていなかった思いを砕かれたあとの絶望のコントラストが強く、自ら死を選んだとも見えるのが今回の上演との親和性を高めた。なかでも井上とのビジュアルバランスや声質のハーモニーがよくあっていて、これは博多座だけの聞き物だった。
 もう1人のルドルフ立石俊樹は、母の愛に飢えた孤独な魂を死に利用されるという、ここ数年のルドルフ像を踏襲した役作り。心もとなさの表出としっかりした体躯がもたらす一種のアンバランス感が、更にルドルフの不安定さにつながって映るのも役柄を支える利点になっている。トートにも、ハンガリーの革命家たちにも利用されているだけでなく、ルドルフ本人が、心のどこにも確たる自信を持てていないのだろうと強烈に思わせるが故に、希望を見出せないままに死にむかっていく立石のルドルフがなんとも切なかった。
もう1人のルドルフ立石俊樹は、母の愛に飢えた孤独な魂を死に利用されるという、ここ数年のルドルフ像を踏襲した役作り。心もとなさの表出としっかりした体躯がもたらす一種のアンバランス感が、更にルドルフの不安定さにつながって映るのも役柄を支える利点になっている。トートにも、ハンガリーの革命家たちにも利用されているだけでなく、ルドルフ本人が、心のどこにも確たる自信を持てていないのだろうと強烈に思わせるが故に、希望を見出せないままに死にむかっていく立石のルドルフがなんとも切なかった。

剣 幸

涼風真世

香寿たつき
皇太后ゾフィーはトリプルキャストで、ただ意地の悪い姑ではなく、結局はこの人の言っていることが最も正しかったのだと思わせる剣幸の威厳。意表を突くふくれっ面まで見せる、どこかで可愛らしい年齢不詳感が炸裂する涼風真世。「宮廷でただ1人の男」に説得力を与えつつ母性も滲ませる香寿たつきとそれぞれに魅力があり、誰にあたっても嬉しい強力な布陣で楽しめる。
 1幕でエリザベートの母ルドヴィカ。2幕で娼館の女主人マダム・ヴォルフを演じ分ける未来優希は、ルドヴィカで適度な鬱陶しさを出しつつ人の好さも滲ませ、マダム・ヴォルフで十全な歌唱力を披露して盤石。女官長リヒテンシュタインの秋園美緒も、この役柄に必要な権高さと歌唱力を存分に発揮してすっかり『エリザベート』の顔の1人になっている。今回の演出で表現が美しさにグッと振れたヴィンディッシュを美しいままに見せた彩花まり。放浪するエリザベートに付き従うスターレイ伯爵夫人の堅実な演技が光る山田裕美子。娼婦マデレーネの鍛え抜かれた美しいボディが輝く美麗をはじめ、彩橋みゆ、華妃まいあ、ゆめ真音と元宝塚出身者が増えていて、エリザベートの姉ヘレネの原広実や、家庭教師の真記子、死刑囚の母の池谷裕子らの、グッとリアルな演じぶりとが織りなす化学反応も楽しい。
1幕でエリザベートの母ルドヴィカ。2幕で娼館の女主人マダム・ヴォルフを演じ分ける未来優希は、ルドヴィカで適度な鬱陶しさを出しつつ人の好さも滲ませ、マダム・ヴォルフで十全な歌唱力を披露して盤石。女官長リヒテンシュタインの秋園美緒も、この役柄に必要な権高さと歌唱力を存分に発揮してすっかり『エリザベート』の顔の1人になっている。今回の演出で表現が美しさにグッと振れたヴィンディッシュを美しいままに見せた彩花まり。放浪するエリザベートに付き従うスターレイ伯爵夫人の堅実な演技が光る山田裕美子。娼婦マデレーネの鍛え抜かれた美しいボディが輝く美麗をはじめ、彩橋みゆ、華妃まいあ、ゆめ真音と元宝塚出身者が増えていて、エリザベートの姉ヘレネの原広実や、家庭教師の真記子、死刑囚の母の池谷裕子らの、グッとリアルな演じぶりとが織りなす化学反応も楽しい。
一方、エリザベートの父マックス公爵の原慎一郎の高い歌唱力は、2幕の「パパみたいに」のリプライズで頻発するどこか不協和音の香りを残す複雑なハーモニーを、歴代でも指折りではないかと思えるほど美しく響かせただけでなく、演技面も充実。エルマーの佐々木崇、シュテファンの章平、ジュラの加藤将は、三人共にスラリとした長身が映えて、ビジュアル力が上がるばかりの現代のミュージカル界、また演劇界の洗練を象徴する革命家チームになった。ツェップスの松井工がそこに渋みをうまく調和させ、ゾフィーの取り巻きである重臣たちの朝隈濯朗、安部誠司、石川剛、後藤晋彦、横沢健司が、それぞれに個性を粒立たせているのも良い対比になっている。またトートダンサーの乾直樹 五十嵐耕司 岡崎大樹 小南竜平 澤村亮 鈴木凌平 山野光 渡辺謙典が揃って長身の上に髪型にも統一感があって、トートの配下のようであったり、また分身のようでもあるといった、それぞれのトートに対して柔軟に表現を変えているのも小㞍健太の振付と併せて秀逸だった。
その柔軟にという意味では、休演者を出しながらもスウィングの廣瀬孝輔、山下麗奈をはじめとした全員が様々に代役に立ち、フォーメーション変更に対応するなど、一丸となって舞台を支える様にはただ頭が下がるばかりで、全体に東京・帝国劇場から福岡・博多座までの道のりで、ひとり一人の役者の演技が格段に深まり、カンパニーの団結力が際立っているのが素晴らしかった。
東宝版初演から22年、今回2022年~2023年での上演で、ミュージカル『エリザベート』がひとつの完成形を見たこと。それでいながらきっと、時代に即してまた新たな顔を見せてくれるだろう可能性も感じさせたことに、深い感慨を覚える、記憶に強く残る公演になった。福岡・博多座での大千穐楽のライブ配信、そして東京・帝国劇場公演の映像化が、より多くの人に2022年~23年版の『エリザベート』を届けてくれることに期待している。
 【公演情報】
【公演情報】
ミュージカル『エリザベート』
脚本・歌詞:ミヒャエル・クンツェ
音楽・編曲:シルヴェスター・リーヴァイ
演出・訳詞:小池修一郎(宝塚歌劇団)
オリジナルプロダクション:ウィーン劇場協会
出演:花總まり 愛希れいか
山崎育三郎(東京公演のみ)古川雄大 井上芳雄(福岡公演のみ)
田代万里生 佐藤隆紀
甲斐翔真 立石俊樹
未来優希
剣幸 涼風真世 香寿たつき
黒羽麻璃央 上山竜治 ほか
●1/11~31◎福岡・博多座
〈博多座公演サイト〉https://www.hakataza.co.jp/lineup/202301/elisabeth/index.php
●2022年10月~11月◎東京・帝国劇場 公演終了
●2022年12月◎愛知・御園座 公演終了
●2022年12月~2023年1月◎大阪・梅田芸術劇場メインホール 公演終了
【商品情報】
2022年キャストBlu-ray/DVD
①愛希れいか&山崎育三郎バージョン
エリザベート 愛希れいか トート 山崎育三郎 フランツ・ヨーゼフ 田代万里生 ルドルフ 甲斐翔真 ゾフィー 剣幸 ルキーニ 上山竜治
②愛希れいか&古川雄大バージョン
エリザベート 愛希れいか トート 古川雄大 フランツ・ヨーゼフ 佐藤隆紀 ルドルフ 立石俊樹 ゾフィー 涼風真世 ルキーニ 黒羽麻璃央
販売価格:各15,000円(税込)2バージョン発売前同時予約特別価格 27,000円(税込)
予約受付中:https://mall.toho-ret.co.jp/category/PREORDER4/
発売日:2023年秋予定
【ライブ配信情報】
① 1月30日(月) 17:00公演(2月6日までのアーカイブ配信付)
エリザベート 愛希れいか トート 井上芳雄 フランツ・ヨーゼフ 佐藤隆紀 ルドルフ 立石俊樹 ゾフィー 涼風真世 ルキーニ 上山竜治
②1月31日(火) 12:00公演(2月7日までのアーカイブ配信付)
エリザベート 花總まり トート 古川雄大 フランツ・ヨーゼフ 田代万里生 ルドルフ 甲斐翔真 ゾフィー 剣幸 ルキーニ 黒羽麻璃央
視聴料金:5,500円(税込)イベント割4,400円(税込・2023年1月31日まで予定。規定予算額に達した段階で早期終了の場合有)
販売期間:
1月30日(月) 17:00公演 1月12日(木) 10:00~2月6日(月) 20:00
1月31日(火) 12:00公演 1月12日(木) 10:00~2月7日(火) 20:00
視聴チケット購入:
uP!!! https://live.au.com/live/254/
TELASA https://live.au.com/telasa/live/255/
【取材・文/橘涼香 舞台写真提供/東宝演劇部】
Tweet