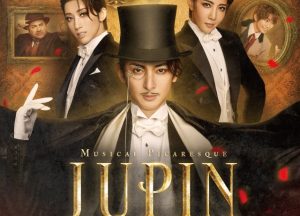芹香斗亜率いる若手の力量を感じさせる宝塚宙組公演『群盗─Die Räuber─』

宙組の二番手男役スターとして躍進著しい芹香斗亜主演公演、宝塚歌劇宙組公演ミュージカル 『群盗─Die Räuber─』─フリードリッヒ・フォン・シラー作「群盗」より─が日本青年館ホールで上演中だ(4日まで)。
ミュージカル 『群盗─Die Räuber─』は、18世紀後半にドイツで起った革新的な文学運動「シュトゥルム・ウント・ドラング」=古典主義や啓蒙主義に異議を唱え、理性に対し感情の優越を主張した作品群が生まれた時代の、ゲーテの「若きウェルテルの悩み」と並ぶ代表作であるフリードリッヒ・フォン・シラーの戯曲「群盗」を、脚本・演出の小柳奈穂子がミュージカル化した作品。封建社会の中で自由への願望を抱いた青年が辿る運命が、非常に若いメンバー中心の座組で描かれている。
【STORY】
18世紀のドイツ。父モール伯爵(凛城きら)の治める領地で、病弱な母シャルロッテ(はる香心)、従姉妹アマーリア(天彩峰里)と共に穏やかに暮らしていた嫡男カール(芹香斗亜)の元に、ある日、母親を亡くした異母弟フランツ(瑠風輝)が引き取られてくる。モール伯爵がほとんど気まぐれのようにひと時情けをかけた女性との間に生まれたフランツは、父である伯爵にも、爵位と領地を当然のように継承するカールにも複雑な想いを抱いていたが、カールは屈託なくフランツを弟として受け入れ、共に剣を学び、競い合って成長していく。
やがて更に広い世界を見たいと望む青年に成長したカールは、父の反対をものともせず、ライプツィヒの大学へと赴く。カールに淡い恋心を抱いていたアマーリアは、「どうしても困ることがあったらそれを売って帰ってくればいい」と涙を隠して母の形見の指輪をカールに手渡すが、まだ見ぬ未来への希望に胸膨らませるカールは、彼女の真の想いに気づかないまま旅立っていく。そればかりでなく、カールは自分の大学進学を後押ししてくれたアマーリアの父であり、足に障害を持つ叔父ヘルマン(希峰かなた)が、爵位と領地を狙いフランツと結託して自分を敢えて故郷から遠ざけたことを知る由もなかった。
新たな世界に足を踏み入れたカールは、ブルジョアジーの子息である学友たち、シュヴァイツァー(穂稀せり)、ラツマン(愛海ひかる)、シュフテレ(雪輝れんや)、ロルラー(なつ颯都)らの自由を求める思想に触れ、意見を闘わすうちに、貴族の嫡男でありながらも啓蒙主義者たちの国政参加を主張する論文を大学に提出するに至る。だが、この論文は当然認められるはずもなく、反体制派と目されてしまったカールの元に、彼の学生生活の現状を知った父から事実上の勘当を言い渡す手紙が届く。絶望するカールだったが、学友たちと夜な夜な繰り出していた酒場で旧知の仲となっていたシュピーゲルベルク(秋奈るい)に「これでお前は貴族でなくなった代わりに、それ以外の何にでもなれる本当の自由を得たんだ」と煽られ、その言葉のままに、富める者から奪い、貧しい民たちに分け与える義賊集団、正義の為の犯罪者、善意の盗賊の群れ「群盗」となることを決意。学友たち、シュピーゲルベルク、その恋人リーベ(華妃まいあ)、リーベの弟グリム(湖々さくら)らと共に、盗賊行為を働き民衆に金品をばら撒く。
その血気盛んな行動により、「群盗」はたちまちにして反体制派の英雄に祭り上げられていく。 だが、「群盗」の首領=カールが貴族の嫡男だと公表されるや否や、裏切られたと思った民衆は一転してカールと「群盗」たちを敵視するようになり、軍隊と民衆双方から追われる身となった「群盗」たちは、ボヘミアの森の奥深くに辛うじて逃げ延びる。そんな四面楚歌の彼らの元に仲間に加えてくれとモール領の青年コジンスキー(風色日向)がやってくる。父モール伯爵亡きあと、フランツとヘルマンが過酷な重税を課し領民を苦しめていること、更に、そもそも自分の勘当は二人の謀り事による偽りだったと知ったカールは、囚われの身同然だというアマーリアを救い出す為、危険を冒して故郷に戻る決意をするが、それはカールを密かに愛していたリーベの心に重い楔を打つ行為となり……

若者たちが理想を求め、高い志から体制に反旗を翻す行動に出ることは、歴史上数多の国の様々な時代で繰り返されてきた。日本にも学生運動の嵐が巻き起こった時代が約半世紀前にあったし、演劇の世界で取り上げられているものとしては、現在最も広く親しまれているミュージカル『レ・ミゼラブル』の劇中で、アンジョルラスをリーダーとした学生たちの蜂起が印象深く思い出されるだろう。彼らの決起がもたらした結果や、理想の世界を求める為に選んだ手段の是非を軽々しく語ることはもちろんできないが、その出発点には確かに高い理想があり、そこまで崇高な理想に満ちた世界を、この世に創り出すことが可能なのか?という疑問を持たないまま、彼らをひた走らせたものが「若さ」だったことは、いずれの国のどの戦いにも共通していたのだと思う。 そんな傍から見ればほとんど計画性もなく、民衆が自分達に加担すると無邪気に信じ、理想さえ高ければ犯罪をも神聖な手段になると思い込んだ彼らの行動が、それでも確かに胸を打つのは、ほとんどの「大人」がすでに、今の世の中にあらゆるしがらみを持っているからだ。生きていく為に不可欠のそれらに縛られて、どんなに心の底には不満を抱えていようとも、理想だけを頼みに行動を起こすなどということは、夢にも考えられない大人の目から見れば、彼らの蛮行はあまりにも眩しい。
だから105年間、非常に大きく括れば現実にはあり得ない美しい愛や、気高い魂や、厚い友情を描いてきた宝塚歌劇に、このシラーの「群盗」の世界が全く似合わないものだったとは思わない。むしろ若さ故の無分別、衝動に任せて突き進む行動に美点を見出すという意味においては、宝塚ほど相応しい世界は他にないとも言える。更に、『ルパン三世』や『はいからさんが通る』と言った有名漫画原作作品を巧みに宝塚化してきた小柳奈穂子が、礼真琴に『かもめ』芹香斗亜に『群盗』と、宝塚の次代を担う人材にこうした文芸作品を敢えて持ってくることにも、スターをより高みへと成長させたいという想いがあるのは容易に推測できる。観客がスターの美しさ、カッコよさ、完成された非現実感を求める傍らで、スターの成長物語を見守る側面も確かに有している宝塚歌劇の在り方とも、その想いは乖離したものではない。

ただ、やはりひとつ気になるのはシラーの『群盗』という作品自体が、シラーが初めて世に出した戯曲であり、後年作者本人が認めているようにかなりの部分で粗さがあるということだ。ドイツ文学の「シュトゥルム・ウント・ドラング」時代を代表するゲーテの「若きウェルテルの悩み」とシラーの「群盗」との知名度に、現在明らかな開きがあるのは、小柳がプログラム掲載の作者言で述べている、後者が上演されなければ触れる機会の乏しい戯曲だからだ、という理由だけではやはりないと思う。何よりも厳しいのは、主人公が周りの人々の口に出さない想いを感じ取ることができず、ほとんど行き当たりばったりに他人の意見に流されていくようにしか見えないことで、そこに美点や普遍性を見出すのを難しくしている。それでもこの作品に熱い賞賛が集まったのは、発表された当時のドイツの時代の風と合致したからに他ならず、謂わばこの作品は時代の産物といった存在なのだろう。
そう考えるとずいぶんと難しい作品を選んだものだなと感じざるを得ないし、前述した作者言全体を通しても、小柳の頭でっかちに近い気負いが迸っていて、娯楽作品を追求することも決して悪くないばかりか、それを貫けるのも真に選ばれし才能の持ち主だよ、と肩を叩きたいような気持ちにもなった。現実にこのカール役で作品を支える任を負った芹香の負荷は大変なものだっただろう。トップスター真風涼帆を中心とした宙組の主要メンバーのほとんどが博多座公演に行っていた中で、極めて若い座組を率いての主演にもなっていたから尚のことだ。
けれどもその芹香が抜群の求心力で舞台を引っ張ったことが、すべてを昇華している。花組から宙組へと二番手男役としての組替えを経てきた芹香の、寡黙な難役から軽い遊び人まで振り幅の大きな役柄を演じた経験が生き、人を疑うことを知らない貴族の御曹司が辿る運命を、宝塚のスターが演じる二枚目役として力技でねじ伏せたのはたいしたもの。立場を異にする毎に変わっていく様々なテイストの衣装も美しく着こなし、カールをヒーローの座に踏み留まらせた、スター芹香の成長を感じさせる主演になった。
ヒロイン・アマーリアの天彩峰里は、出てくる度に置かれている状況が変わっている役柄に、芝居心でただひたすらカールを想い続けるヒロインとしての芯を通している。終盤の展開は本来宗教色がかなり強く、日本人には理解しにくい部分が大きいのだが、アマーリアの行動を募り過ぎた愛故に見せたところに、娘役天彩峰里の真骨頂が発揮されていた。

カールの異母弟フランツの瑠風輝は、原作よりは宝塚のスターが演じやすいように役柄が寄せてあるとは言いつつも、若手男役にはかなり難しい役どころに果敢に体当たりした役者魂を評価したい。本来の持ち味に野性味があるのも助けになったし、特に芯を取ったフィナーレナンバーで、バウホール公演『ハッスル・メイツ!』時点よりも、格段にショーシーンの真ん中力を上げたことが見て取れたのが嬉しい。この作品の経験もまた瑠風の糧になることだろう。
物語の語り手の任を担ったヴァールハイトの鷹翔千空は、くっきりとした口跡で複雑な作品の解説役の大任を果たしている。物語世界を俯瞰していながら、小役人として作中の登場人物でもあるヴァールハイト自身も成長していく過程も巧みに表現していて、この役柄もかなり難しいと思うだけに、改めて実力派だと感じさせた。
もう1人、第二ヒロインと言っても差し支えないほどの存在が、ライプツィヒに出た後のカールと関わるリーベの華妃まいあで、彼女が「群盗」に参加したのは世の中の不平等を変えたいという想いからではなく、ただカールの傍にいたかったからだろうと思わせる、溢れる恋心の表出が巧み。これがあるからこそラストのリーベの行動にも得心がいき、大人っぽい役柄を担当することが多い人だが、十分に可憐でひたむきな娘役ふりが際立っていた。
また、大きな役柄が多いのが、この作品の1番の美点ではないかと思えるほど大役が多く、宙組若手が与えられた機会を着実にこなしていて頼もしい。

カールをある意味で扇動していくシュピーゲルベルクの秋奈るいは、「群盗」の中で唯一ブルジョアジーでないことのコンプレックスが、役の行動にないまぜになっていることをきちんと見せているし、シュヴァイツァーの穂稀せり、ラツマンの愛海ひかる、シュフテレの雪輝れんや、ロルラーのなつ颯都が、「学生たち」「仲間たち」に留まらないそれぞれの個性を的確に表現。歌のソロも銘々達者に聞かせ、宙組の未来は明るい!と感じさせてくれる。リーベの弟グリムの湖々さくらも、非常に重要なポジションの少年役をリリカルに演じきったし、後半の展開に欠かせないコジンスキーの風色日向も役割をよく果たしている。カール、アマーリア、フランツの幼年時代を演じた碧咲伊織、陽雪アリス、真白悠希も、それぞれの関係性を表わす芝居で、物語に寄与した。
中でも、専科勢の応援を頼んでも不思議ではないというほどの大役、モール伯爵の凛城きらが、厳格な貴族の父親が表に出すことの出来なかった息子への愛情を示せば、その弟であり宝塚版のキーマンとも言える役割を担ったヘルマンの希峰かなたが、立場と健常な肉体を持たずに生まれてきた伯爵家の弟の、捻じれに捻じれた想念を見事に演じて、影のMVPとも言える出色の出来。貴族社会の負の面を体現したオイゲン公の水香依千、病弱なこの人の脆さが全てのはじまりになることを美しく示したシャルロッテのはる香心、それぞれピンポイントの重要な場面で存在感を発揮したズーゼルの花音舞、フロイデの愛咲まりあ、モーゼル牧師の風輝駿も印象に残った。
そして、日本では年末恒例の楽曲ともなっているベートーヴェン作曲交響曲第九番(「合唱つき」)の終楽章で歌われる「歓喜に寄す」(喜びの歌)の原詩を書いた詩人がシラーその人だという、おそらく「群盗」の何倍も知名度が高いだろう、作家のアピールポイントに寄せて、「歓喜に寄す」を中心にクラシックを多用した音楽面の試みが面白かっただけに、いっそ統一しても良かったようにも思う。と、様々な意味で実験的な部分の多い作品を、美しい装置で彩った稲生英介や、照明のベテラン勝柴次朗などのスタッフワークが支え、宙組生としての芹香斗亜初主演作品に宝塚歌劇らしさ加味したことを多としたい舞台となっている。
〈公演情報〉
宝塚歌劇宙組公演 ミュージカル 『群盗─Die Räuber─』─フリードリッヒ・フォン・シラー作「群盗」より─
脚本・演出◇小柳奈穂子
出演◇芹香斗亜 ほか宙組
●2/26~3/4◎日本青年館ホール
〈料金〉S席 7,800円、A席 5,000円
〈お問い合わせ〉宝塚歌劇インフォシメーションセンター[東京宝塚劇場]0570-00-5100
公式ホームページ http://kageki.hankyu.co.jp/
【取材・文・撮影/橘涼香】
Tweet