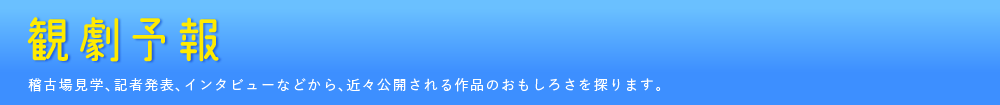serial number公演、アーサー・ミラーの傑作『All My Sons』いよいよ開幕! 詩森ろば×神野三鈴×田島亮 インタビュー

詩森ろばと田島亮のユニットserial numberの新作舞台が、10月1日から三軒茶屋のシアタートラムで幕を開ける。(10月11日まで)
今回は翻訳劇で、アーサー・ミラーの初期の傑作『All My Sons』。第二次世界大戦後のアメリカを舞台に、欠陥部品を納品したことで、たくさんの若者を死に至らしめた飛行機部品工場の経営者一家を中心に描いている。
資本主義の陰影、父と息子の葛藤、子供の死を信じられず家庭を機能不全に陥らせている母など、極めて現在的なこの物語を、今回は演出の詩森ろば自身が、翻訳も手がけた。
出演は、2020年の読売演劇大賞最優秀女優賞が記憶に新しい神野三鈴、劇団壱組印を主宰、映像でも活躍する大谷亮介ほか、充実のキャスト陣で新たな息を吹き込む。また、2011年にこの作品に出演して高い評価を得た田島亮が、9年の年月を経て再び同じ役に挑むことでも注目されている。
稽古が中盤に差し掛かった時期、翻訳・演出の詩森ろば、母ケイト役の神野三鈴、長男クリス役の田島亮という3人に、作品の内容や役柄、そしてこのコロナ禍における演劇についても話をしてもらった。

田島亮 詩森ろば 神野三鈴
「みんな我が子」という真の意味が今こそ必要ではないかと
──今回、詩森さんがこの作品を上演したかった理由から話していただけますか。
詩森 私はアーサー・ミラーが好きで、それからユージン・オニールとか、あのへんのアメリカの作家が好きで、『All My Sons』は2011年に田島さんが出ていたのを見て、面白い戯曲だなと。とくにケイトという女性、この人がとても面白い。それで田島さんと、もしこの作品を上演するならと夢キャストを話し合ったりする中で、ケイトは神野さんという話が出て来て、それで思いきって神野さんにお願いしてみたら受けていただけて、実現することになりました。
神野 私はまず、私を見つけてくださって、この作品を一緒にやりたいと思ってくださったことに、本当に感謝しています。お二人がserial numberを作られて、作品を次々に作っていることは、とても新しいことだと思いました。私はいつもいろいろなカンパニーからオファーをいただいたときに考えるのは、一緒にやって楽しくなれるかということなんです。舞台って1年にそう何本もできるわけではなくて、私の今の体力ですと3本が限界で、ですからどの作品を選ぶかというのはとても大事なことなんです。でもお二人がこの話をしに来られたとき、演劇に対する純粋な愛情が感じられて、すごく愛おしいなと思いました。また、詩森さんの活動を拝見していて、この人はこれからさらに演劇界で大事な存在になると思ったし、田島さんのこれまでも伺って、今、彼がすごくがんばっていらっしゃるなと。そういうお二人に指名されたのならお受けしなくてはと。
──そういう意味では、詩森さんは映画の脚本でも受賞して、神野さんは今年の読売演劇大賞 最優秀女優賞と、まさにビッグな顔合わせになりました。
詩森 でもオファーは3年前で、serial numberも海のものとも山のものとも知れない状態のときだったんですけどね(笑)。
──作品そのものについては神野さんはどんな印象がありましたか?
神野 お話をいただいたとき、詩森さんと田島さんと作品についてもいろいろな話をしたのですが、この戯曲には社会の矛盾がすごく詰まっていて、その中で命を繋いでいく母性というもの、もしかしたら夫も我が子に入るなとか、「All My Sons」というタイトルの真の意味が今こそ必要なんじゃないかと、そういう共通の思いを感じました。
神野さんは身体と知、両方を持っている人
──田島さんは夢キャストだった神野さんと共演することになっていかがですか?
田島 この作品は僕にとってすごく思い入れのある作品だったので、本当に夢として、神野さん出てくれたらすごいよねと言っていたんですが。
神野 そんな有り難いことを。今、後悔してるでしょ(笑)。
田島 いえ! いつも神野さんの舞台を観ていると魔法のようで、どうやったらこんなことができるんだろうと思っていたのですが、今、稽古で目の当たりにすると「あ、魔法じゃなかったな」と。すごく積み上げてきたものとか、ロジカルに考えていらっしゃるところとかがわかって、だからできるんだなと。すごく勉強になります。
──神野さんは役によって見せる顔が毎回違って、本当に天才肌の女優さんですね。
詩森 本の読み方が違うんです。日本だと感性みたいなものが尊重されることが多くて、ロジカルに読む人だとロジカルさだけが出て来たりしますが、でもちゃんとした人はロジカルに読んでそれを肉体に落としていく。そういう作業が出来る人で、とくに女性でそれが出来る人はわりと少ないと思います。ですから信頼できるし、一緒に企んでいける。感性とか感覚が優れている素晴らしい女優さんはいっぱいいるんですけど、でも一緒にやりたかったのは、身体と知、両方持っている方だったので、一緒に稽古しながら、こういうことだったんだなと。
神野 その同じことを私も詩森さんに感じています。戯曲を一緒に掘り下げていけるし、ディスカッションできる。稽古の中で沢山発見があるんです。そしてものすごく人間に対する愛情がある。今回、詩森さんとご一緒して、ロジカルに台本を読みながらも感性の部分でキャッチする方で、でも一番大きいのはその先で、何を自分たちの伝えたいものとして選んでいくか、私たちがこの作品をやる意味みたいなものを共有できる。こういう方がいてくださった喜びがすごくて、だから何でも話し合っていきたいし、勝手に長く付き合うぞと思っているんです。
詩森 こちらこそ!
神野 やっぱり出会いの時期って大事で、会うべきときに出会えたんだなと思います。

翻訳をすることは演出家にとって良い経験になる
──そして今回、翻訳も詩森さんがされたそうですね。
詩森 私は親に小学校の1年生から高校生まで英語を習わせてもらったので、その恩返しをしたいとずっと思っていたんです。今回、2回目の翻訳なんですが、できれば演出家は翻訳もしたほうがいいと思いました。もし自分の翻訳を使わないにしても、海外戯曲を翻訳することは演出家として、すごく自信になります。一言レベルで解釈をしないと進めないという体験はとても良い経験になるので。
──詩森さんの翻訳台本で稽古していて感じることは?
神野 英語ってすごくロジカルなところがありますよね。そして感情が激高するほどに、相手の優位に立とうとするときほど、ロジカルになるんです。ロジカルに言える人間が勝つ。一方で日本語独特の感情というのがあるのですが、今回のろばさんの訳は英語の文法で訳されていて、へんに日本語に作り換えていないんです。そのぶん最初にそれを言うときは、日本語の文法と違うので脳の動きがちょっと違って、慣れなかったんですけど、でも実際に言葉にして相手役と対峙すると、それがもう演出の第一歩目になっていて、ああなるほど思います。ここでこういう言い方をする、ここで同じ言葉をこう繰り返す、そこを端折ってないし、日本語らしい文体にしていない。でも選んでいる言葉がやっぱり劇作家の言葉なので、日本語力がある言葉になっています。私は他の訳にすごく詳しいわけではないのですが、ろばさんのこの翻訳はアーサー・ミラーの戯曲がすごく豊かに伝わるものになっていると思います。もちろんそれを役者がものにできたら、ですけど。
──上演台本を読ませていただいたら、人間関係や力関係がとてもわかりやすくて、1人1人の人間像が伝わりやすいですね。
神野 この戯曲自体が翻訳劇によくある敬語がなくて、生活の言葉で書かれていて、俳優たちがリアルに発せられるようになっています。そしてアーサー・ミラーならではの当時の社会や時代のいろいろな問題が後ろに隠れています。そこにだけ奉仕してもダメですし、それが目的ではないのですが、そこに血と肉を通わせることができればと。
書かれてから100年近く経って時代は複雑になっている
──田島さんはこの戯曲は二度目ですが、やっと役の年齢に追いつきましたね。
田島 最初のときは24歳でクリスをやったのですが、この作品はすごく大好きで、いつかこの役の年齢でやったらどうなるんだろう?と想像したりしていたんです。でも今、同年齢になって改めて読んでみると、自分よりすごく大人の部分を持っているなと。
──弟ラリーの手紙の中に、当時の前線の兵士の意識と経済主義の国策との乖離を批判する部分がありますね。クリスは戦争をどう捉えていたのでしょう。
田島 あの戦争では、アメリカと日本では戦争への姿勢というか意識に根本的な違いがあったと思うんです。アメリカ人は経済的には戦争に関わっても直接参戦したくなかった。でも参戦しなければならない状況になってきて、じゃあ兵士たちは何のために戦うんだと。理由がないと戦えないわけで、その何かが世界の平和を守ることであり、正義、ジャスティスのために戦うということが、兵士には必要だったんです。そして実際にクリスは、彼より強く正義を信じて戦っていた兵士たちの死という現実を持って帰ってくる。そう考えると父親を許せないだろうなと思います。
詩森 ただ今回作っているのはちょっと違っていて、田島さんが24歳のときにやった作品は、明らかに正義があって父親を糾弾するというような内容だったと思いますが、私はもう少し複雑なコンテキストのある作品にしようと思っていて、そのために今、稽古場でみんなで格闘しているところなんです。
田島 そうですね。今回は、父に「なんでそんなことをしたんだ」と責めるというより、その怒りの対象には自分も含まれている。そういうところをすごく感じます。
──アーサー・ミラーの他の作品でも父と子それぞれの正義と、それを取り巻く社会や時代の変化などが描かれていますが、今回はもう少し背景や心情が複雑なのですね。
詩森 この作品をアーサー・ミラーが書いたのはクリスと同じ32歳で、クリスの目線で書いているのだろうなと。でも私はもう少し上の世代で。たとえばバブルの時代も知っていて、それが弾けるのも見ました。つまり資本主義の光の部分も見てしまった世代なんです。だからそれに塗りつぶされてしまったジョーという人物、その人と一緒に生きているケイトという人が、単純な正義みたいなもので片づけられない。社会構造の狭間に落ちていった犠牲者の感じがしているんです。だからクリスについても、戦争に行ったときに自分もつらい体験をしたことで、お父さんは間違っているという話ではなく、自分の罪にも気づくみたいな、もちろん都合よくは書きたくないのですが、それぞれがもうちょっと自分の中に戦争があるという認識が、今一番必要だと思っていて。戦争は外にあって資本主義は汚いものとして糾弾するとか、間違っているとか言うだけでは、アーサー・ミラーの時代から100年近く経った今、単純にその構造だけでやってはいけないんじゃないかと思ったんです。というようなややこしい、難しいことを私が言っているので、稽古場のみんなが今すごくがんばってくれているんです(笑)。

21世紀のピエタをやらせてもらえるのだとしたら
──ケイトという役ですが、夫の問題もありますし、次男の死を受け入れていないのに、長男はその婚約者と結婚すると言い出す。いろいろなものを抱え込んでいますね。
神野 私は、今の段階でなのですが、ケイトは時々バランスを崩して自分の世界に入っていくのですが、その入り口が薔薇の花の香りで、現実逃避するんです。それは私の姿でもあって、世の中の矛盾、今までは豊かさが幸せであると教え込まれて、ブランドや消費経済の世界を当たり前のように生きてきた。今、その豊かさが幸せではないということに気づいてしまって、自分の手が綺麗ではないことにも気づいてしまった。今もモーリシャス沖の日本のタンカー事故のことで、できることならイルカを1頭でもこの手で救いたいと思いましたし腹を立てました。でもあの重油から作られる沢山の物、たとえばこのペットボトルもそうですよね。つまり私の手も汚れているわけです。そこに気づいたときもう逃げ場がない。諦めしかない。でもケイトは「だってしょうがないじゃない。それが幸せなんだから」とごまかせなかった人で、彼女は生きていくために、ああして彼女自身のバランスを崩して自分を生かしている。
そして、私はこの作品のここが凄いなと思うんですが、命が命を守る、生き続けるというのが大前提にあるんです。そうだここなんだなと思って、今、稽古で探っているのですが。つまり、狂ってしまって命を断てばいいわけです。男たちはみんな命を絶ってます。クリスは生きてるけど大丈夫かわからない状態です。でもケイトはぎりぎりのところで生きていくべく心を決めるんです。そういう意味で今回のこの『All My Sons』で言いたいのは、このコロナを経て、絶対に前に進まないといけないということで、でないとみんな死ぬんです。最後のシーンで、クリスが何か言おうとするとき、ケイトはそれを「静かに」と止めて、「忘れるの。そして生きるの」と言うんです。矛盾を内包したまま。あれ「ピエタ」ですよね。
詩森 そうです。
神野 生け贄のようにクリスを持って、でもその生け贄を生け贄にしてたまるかという思いでやってます。私は21世紀の「ピエタ」をやらせてもらえるのだとしたら、狂っていようがどうであろうが、この息子たち、All My Sonsを犠牲にして進んでいってはいけない、それはもう限界と。この戯曲はそこまでしか書かれていないので、観た方にこれは救いのない話で終わってしまったの?と思われないように、何かをそこに残したいと思っています。その強さと諦めなさを。今、それをどうやったらいいのか考えてて、シンドイです(笑)。
田島 ああ、そこまで考えているんだ!
──そう伺うとこの作品は、とにかく生き延びようという、そのメッセージなのですね。
詩森 登場人物たちはこのあとハッピーに生きられる気はしないのですが、やっぱり一番伝えたいメッセージは、こんなに絶望があるよではなく、生きなきゃということが渡せる作品にしたいなと思っています。
神野 ケイトは生き抜くために薔薇の花の香りで自分に魔法をかけて、それは愛であったり母性であったりするのですが、そうやって矛盾を越えてきたと思うんです。ただその矛盾を全部息子が背負ってしまった。すごいあそこで重いんですよ、息子が体中ゆだねてくる。それを感じながら「この重さをごまかしていていいの?お母さんたちはどう思いますか?」という気持ちでいます。あそこの英語の訳はすごく難しい。「あなたが生きている限りラリーも生きている」とケイトは言うんですが、英語だと「あなたが生きている限りboyも生きている」で、しかもmy boyではなくboyなんです。ということは、私が言う「ラリー」という言葉には、戦争で犠牲にならなきゃいけない沢山の子どもたちの名前が入らなくてはいけないんだと。執筆当時のアーサー・ミラーがあえて「ラリー」と書かずに「boy」と書いたのは、若い彼なりの強烈なメッセージがあったと思います。ろばさんもそこは悩まれて、でも「ラリー」と書かれた。その言葉をどうやったら肉体化できるのかなと一生懸命考えてます。
──観ている人たちの目に沢山のboyが見えるようにと。
神野 そう。でもそれは私自身に見えてないと見えないだろうと。そのためには最初の1シーン目から、ろばさんが訳してくださった言葉で豊かに豊かに、目の前にこの物語の風景が見えないと。劇場がアメリカにもなるしロシアにもなるのが演劇で、MAGICの箱ですから。せっかくこのコロナの中で観にきてくださる人たちに、そこでやっぱり魔法を見せたいんです。そしてそれぞれ何かを持ち帰ってもらう。それをちゃんと果たせないとコロナの後、人が戻ってくるのが難しいなと思います。そのためにも私たちは豊かな創造の世界を創り出したいと思います。
劇場は私たちの生きる場所という当たり前のことを
──詩森さんも上演決定には、やはり覚悟がいったでしょうね。
詩森 だからこそこの作品で本当によかったと思います。こういうことが起きてから選んだのではなく、たまたまこの作品がこの時期になった。それでよかったと思うし、そういう意味では幸運でした。やる必要のある作品をやるべき時期にやりたいと思っているので。
神野 私たち表現する側は有事のときに、不安な人たちに身体を差し出す側で、「私にできることは?何ができる?」という、そこにいないと普段の精神って保てないと私は思っているんです。だから今回これをやることは偉いことでもなんでもなくて、こうして集まっている人たちが、一緒にみんなで「今なにを私たちする?」という、それだけのことなんです。
──コロナ禍の日々の中で、改めて演劇は光だなと思いました。劇場が1つずつ開いていくたびに光が増えていくなと。
詩森 今は採算なんて取れないですよね。みんなわかっているんです。劇場はお客さまのものでもあるのですけど、私たちの生きる場所だったんだという、ここがないと生きられないという当たり前のことを、今回改めて感じていて、だったらやっぱり客席に還元していかなくてはという気持ちですね。
神野 井上ひさし先生がおっしゃっていたんですけど、どこから来たか誰なのか知らない同士が集まって、一緒に笑って泣いて、またバラバラに散っていく。そしてそれぞれそこで貰った種を持ち帰っていく。こんな不思議な共同体は劇場にしかないと。ここは特別な場所だと。そして私たち1人1人がそこから世界に繋がっている。それを肌で感じられるのが劇場なんですよね。
詩森 演劇を滅ぼすのかと思ったコロナですけど、でも演劇は死なないです。逆にこういう困難があるとき、芸術家は別に不幸じゃないんです。だってリアルなものを1つ貰えるわけですから。
神野 そうなんですよ。
詩森 これを生かさないと、と思います。例えば戦争をしている国からきた演劇を観たりすると、身体の勁さとか思いの強さとか、その強度はちょっと羨ましいんです。だから私たちも今、そういう中にいるんだと。
神野 そして、私たちの舞台がわざわざ危険を冒してまで観に来てもらう価値があったかどうかふるいにかけられるし、この後の状況を育てるのではないかと思うんです。だから恐いですよ。すごく。でもお客さまも自分たちが行かないと劇場がなくなるという気持ちで来てくださるので。
田島 僕もserial numberの6月の公演が延期になったので、今回、稽古初日には「今、俺稽古に向かってるんだ!」という思いがありました。今も稽古できていることに新鮮な感動があります。話がちょっとズレますが、稽古場でおふたりを見ていると、こういうろばさんは見たことないなと、そういうのがあるんです。いつもろばさんが言っていることを、神野さんがそのまま体現されているから、そうか!あるべき姿はこうなんだと。ろばさんが先頭に立たなくてもエネルギーを出せるというか、パートナーがいて作っていくということはこうなんだというのを見て、僕も必死で食らいついていかなくてはと思っています。
神野 田島さんがそうなられたらserial numberは本当にすごくなるから、がんばってください!
田島 はい。

神野三鈴 詩森ろば 田島亮
かんのみすず○神奈川県出身。名だたる舞台演出家からは難役を任され、チェーホフ、テネシー・ウィリアムズ、別役実らが紡ぐ伝説的戯曲にも出演。 井上ひさし作品群にも欠かせない女優。舞台で真の髄まで鍛えられたその存在感と演技によって、映像作品にも活動の場を広げている。第47回紀伊國屋演劇賞個人賞、Asian Academy Creative Awardsの日本代表主演女優賞、第27回読売演劇大賞最優秀女優賞などを受賞。
しもりろば○岩手県出身。1993年、劇団風琴工房旗揚げ。以後、2017年まですべての脚本と演出を担当。2018年よりserial numberとして活動中。他劇団への劇作も多数。これまでに作家協会新人戯曲賞優秀賞、読売演劇大賞優秀作品賞、第51回紀伊國屋演劇賞個人賞、芸術選奨文部科学大臣賞新人賞など多数受賞。2020年には映画『新聞記者』で日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞した。
たじまりょう○神奈川県出身。2008年芸能界デビュー。ドラマ、舞台などに出演。4年間の俳優休業の後、風琴工房「penalty killing」で俳優復帰を果たす。2018年よりserial numberとして活動。映画の制作者としても活動中。最近の舞台は、serial number『serial numberのserial number』『アトムが来た日』『機械と音楽』『コンドーム0,01』、流山児★事務所『コタン虐殺』など。
 【公演情報】
【公演情報】
serial number05
『All My Sons』
作:アーサー・ミラー
翻訳・演出:詩森ろば
出演:神野三鈴 田島亮 瀬戸さおり 金井勇太 杉木隆幸 熊坂理恵子 酒巻誉洋 浦浜アリサ 田中誠人 大谷亮介
●10/1~11◎シアタートラム
〈料金〉一般前売・当日共6500円 学生4000円 障害者3000円(全席指定・税込・未就学児童入場不可)
※学生・障害者は当日要手帳提示。車椅子スペースは劇団のみ取扱い
〈お問い合わせ〉sons@serialnumber.jp
〈公式サイト〉https://serialnumber.jp/allmysons.html
〈公式Twitter〉https://twitter.com/serialnumber601
【取材・文/榊原和子 撮影/田中亜紀】
Tweet