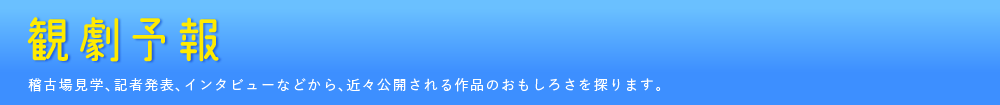野村萬斎オペラ初演出!全国共同制作オペラ 喜歌劇『こうもり』取材会

文化庁の助成を得て、全国の劇場・音楽堂、芸術団体が高いレベルのオペラを新演出で共同制作するプログラム「全国共同制作オペラ」が、2023年オペレッタの最高傑作ヨハン・シュトラウスII世の『こうもり』を上演する。11月に滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホールと、東京芸術劇場コンサートホール、12月に山形のやまぎん県民ホールで上演され、2020年に開館したやまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)の「全国共同制作オペラ」初参加となる。
演出はびわ湖ホールに開館当時から縁の深い、狂言師・俳優・演出家として数々の舞台作品を手掛ける野村萬斎が務め、これが初のオペラ演出となる。指揮は欧州40に及ぶ歌劇場で手腕を発揮してきた、びわ湖ホール芸術監督、山形交響楽団常任指揮者の阪哲朗。主演のアイゼンシュタインに日本が誇るテナー歌手・福井敬。オルロフスキー公爵に幅広いレパートリーで活躍するカウンター・テナーの藤木大地。アデーレに人気ソプラノ歌手・幸田浩子ほか、多彩な歌手が集結。新たな『こうもり』の創造が期待されている。
そんなオペレッタ『こうもり』の記者会見が、5月2日東京芸術劇場で開かれ、演出の野村萬斎、指揮の阪哲朗、キャストを代表して福井敬、藤木大地、幸田浩子が登壇。公演への抱負を語った。

幸田浩子 阪哲朗 野村萬斎 福井敬 藤木大地
【登壇者挨拶】
 野村萬斎 この中では一番珍獣な私が先に話させていただきますけれども(笑)、びわ湖ホールさんとはオープニングの時から様々な作品、古典の表現から新作もさせていただいてきました。そのご縁から今回オペラの演出もということで、まぁ勇気があるなという感じもしないでもないですけれども(笑)。私は世田谷パブリックシアターで20年間、芸術監督をやってちょうど去年でしたか卒業致しましたので、違うジャンルにも挑戦したいな、またこれから勉強したいなという思いもあって、そういった時にクラシック音楽、オペレッタというキーワードが私にとって非常に新鮮だったので、今回阪さんをはじめ皆さんにいろいろ教えていただきながらさせていただこうと思っています。
野村萬斎 この中では一番珍獣な私が先に話させていただきますけれども(笑)、びわ湖ホールさんとはオープニングの時から様々な作品、古典の表現から新作もさせていただいてきました。そのご縁から今回オペラの演出もということで、まぁ勇気があるなという感じもしないでもないですけれども(笑)。私は世田谷パブリックシアターで20年間、芸術監督をやってちょうど去年でしたか卒業致しましたので、違うジャンルにも挑戦したいな、またこれから勉強したいなという思いもあって、そういった時にクラシック音楽、オペレッタというキーワードが私にとって非常に新鮮だったので、今回阪さんをはじめ皆さんにいろいろ教えていただきながらさせていただこうと思っています。
とは言えせっかく私を抜擢していただいたので、それなりの珍しいものにはしたいなと思っております。「珍しいのはよいこと」というのは世阿弥の教えでございますので、今までの定型をどこまで保ちつつ、どこまで崩す、いえ、崩すことをするつもりはないのですが、日本ならではの発想、狂言ならではの発想というものも生かしたいなと思っています。まあオペラとオペレッタの違いもよくわかっていなかったような状況だったのですが、すごく簡単に割り切れば能と狂言みたいなものかと。もちろん楽しいオペラもあると思いますが、どちらかというと舞台がシリアスなのがオペラで、セリフが入ったりお気楽にやっていいのがオペレッタと伺っておりますので、まさに能と狂言の関係ですから、そういう意味で、遊び心満載でやりたいなと思っています。
私自身の演出活動というのはどちらかというと、やはり日本の芸能のアイデンティティが生きるような演出、というものを心がけておりますし、一方でそうでないものを目指すことも私にとっては勉強ですけれども、とにかく私のオリジナリティの強いものをやった方が皆さん珍しく思ってくださるのではないかと思って、開き直ってやりたいなと思っています。今回はびわ湖ホールさんにお声かけをいただき、そして、東京芸術劇場コンサートホール、やまぎん県民ホールでさせていただくということで、小屋が変わると演出も全部に合うようにしなければいけないので、3ホールを移動するということですから、シンプルなものにしたいなと思っています。
狂言の表現も含めて能舞台というものをずっと使っているわけですし、それから日本人の感覚と劇場の中で、まだ尺貫法というものが息づいております。人間二人が対面するなら四畳半、三人なら三間、それ以上なら四間半という風な空間の区切り方が、人数と尺貫の関係でございます。今回の『こうもり』は最後に合唱も出てきますし、大勢出てくるものなので大きな空間が必要だなと、理屈を言うならそういうことになるわけです。でもそんな理屈は見てりゃわかるというか(笑)、そんな風に空間が伸縮自在になるようなことを、派手なセットや書き割りをなるべく使わないでやってみたいなと。とは言え使う時は書き割りも使いますけれどね、物があまりない状況の中で、歌手の皆様、オペレッタですからセリフも言っていただくので、歌にも集中していただきつつ、シンプルな空間なのでちょっと身体的なことも要求するかもしれませんし、むしろ舞台を日本に移し変えるようなことをやるのではないかと。と、どこまで喋っちゃっていいのかな、というのもありますのであとはちょっと、というところですけれども「オペレッタを観に来たはずなのに?」みたいなことになるかな、そうしたいと思っております。
 阪哲朗 『こうもり』は私が大学に入って、関西のオペレッタをやっている団体でピアニストをさせていただいたり、本番の指揮者がいない時の練習で指揮をさせていただいたりした初めての作品なので、今、本当に懐かしいですし、キャスティングに関しても間違いないと思います。ひとつのオペラ団でやる枠を超えたところで動いていますので。そういう10代の頃からやってきた『こうもり』ですが、「これはもっと歳をとらないとわからないよ」と言われていた年齢に僕もなってきたと思うんですね。何がわからないのかと言うと、楽譜を追っていただけでは形にならないものなんです。それは、結局僕がなぜウィーンに行ったかというところで、オペレッタを振りたかったから学校を卒業してすぐに行って、そのまま5年前まで向こうにベースを置いていました。目標はもちろんウィーンの国立歌劇場とか、そういうものにもあるのですが、フォルクスオパーが僕は大好きで、もう授業をさぼってしょっちゅう公演を観に行っていました。
阪哲朗 『こうもり』は私が大学に入って、関西のオペレッタをやっている団体でピアニストをさせていただいたり、本番の指揮者がいない時の練習で指揮をさせていただいたりした初めての作品なので、今、本当に懐かしいですし、キャスティングに関しても間違いないと思います。ひとつのオペラ団でやる枠を超えたところで動いていますので。そういう10代の頃からやってきた『こうもり』ですが、「これはもっと歳をとらないとわからないよ」と言われていた年齢に僕もなってきたと思うんですね。何がわからないのかと言うと、楽譜を追っていただけでは形にならないものなんです。それは、結局僕がなぜウィーンに行ったかというところで、オペレッタを振りたかったから学校を卒業してすぐに行って、そのまま5年前まで向こうにベースを置いていました。目標はもちろんウィーンの国立歌劇場とか、そういうものにもあるのですが、フォルクスオパーが僕は大好きで、もう授業をさぼってしょっちゅう公演を観に行っていました。
当時はオペレッタがいっぱいあって、ハンガリー語とドイツ語が混ざったような作品もありました。そんな中でオペレッタはなかなか難しいとされていると思います。映画の前の芸術のオペラより新しくて、ミュージカルほど新しくなく民族音楽色、民族色が出ている。特にこれはドイツ語だけですし、ワルツが多く取り入れられています。ヨハン・シュトラウスよりあとの作曲家はちょっとまた違う、ミュージカルに移行していくようなものになるので、その橋渡しというのかな。つまり何が難しいって、きっと芝居ができて、踊れて歌えて、その総合力が勝負になるところです。ここにおられる方々は芸達者な方ばかりなのでそこはすごく楽しみにしています。僕もおそらく観ていた以上の数は振っているので、どんな演出が来ても対応しようと思っています。
今回萬斎さんとご一緒できるということで、30年近く向こうにいると能や狂言に触れるチャンスが本当になくて、日本語を喋っていますけれども中身が外国人みたいな(笑)、先ほどおっしゃったアイデンティティはどこだということを考えていました。ここに萬斎さんがおられるからではなく、ここ最近本当に興味があったんです。オペレッタの危険なところというのは自分達が楽しんで盛り上がってしまって、外からどう見られているかの視点が抜けてお客様が置いてきぼりになる恐れがあるところなので、それをこのベテランのキャスト陣でどうやっていくか。「ウィーンの人は右目で笑って左目で泣く」というお話がありますが、それは京都に近いところもあると思いますし、どっちも本当なんでしょうけれども、芸術のすごく大事なところな気がしていて。モーツァルトの長調だけれども悲しさもあるし、悲しいからと言って悲しいだけじゃないところは「和」や「洋」とは関係ない本質な気がするんです。
今「できるだけシンプルな形で」という萬斎さんの演出プランを僕も皆さんと同じで、初めて聞かせていただいたので、ますます楽しみになっています。シンプルというのは結局無限に想像力の幅が広がるということでもありますし、もし日本に舞台を移したとしたら鹿鳴館のような時代のね、ワルツはワルツとして音楽は残るでしょうから、ちょっと日本風のテイストを入れてワルツをどう関連づけられるか。芝居を見ながらどのタイミングで音楽を入れるか、このタイミングでこんな種類の音楽をというのは、例えば映画監督なら作曲家に対してすごく注文をつけると思うんです。それを萬斎さんと一緒に、音楽のスピードと芝居のスピードをどうシンクロさせるのか、或いは音楽のテンポに芝居をシンクロさせるのか、その作業は、AllegroなのかModeratoなのかという話ではなくて、拍ごとに現れたりするんです。そこが僕は本当に好きで。オペラもオペレッタも大好きなので、歌手の方々の意見で、「ここはもうちょっと待った方が面白くなるよ」とか「どういう風にすれば面白いか」というような、クリエイティブな作業を本当に楽しみにしております。
 福井敬 アイゼンシュタインを演じさせていただきます。今お二人のお話をお聞きしてどんどんハードルが高くなってくるのを感じながら、どうしようかという気持ちなんですけれども(笑)、このヨハン・シュトラウスII世の『こうもり』には、言えば世紀末の匂い、こんなに馬鹿騒ぎをしている喜劇ではあるのですが、そういう匂いを演じるたびに感じるんですね。また一方で、それこそリヒャルト・シュトラウスのような豊満な音楽も同じ時代に満ち溢れていたりする中で、こういうオペレッタが流行っていたのは、やっぱり時代の危うさなのかなというのをすごく感じながらいつも演じておりました。今回の萬斎さんの演出プランを先日伺わせていただいた時にも、やっぱり世紀末的なところから新しい時代が生まれてくるのをフューチャーしながらやりたい、というようなことをおっしゃっていましたし、萬斎さんもオペレッタは初めてだということで、とても挑戦的ですよね。本当に挑まれているという感じがしていますので、それにこちらがどう応えていったらいいのかを楽しみにしているところです。是非よろしくお願い致します。
福井敬 アイゼンシュタインを演じさせていただきます。今お二人のお話をお聞きしてどんどんハードルが高くなってくるのを感じながら、どうしようかという気持ちなんですけれども(笑)、このヨハン・シュトラウスII世の『こうもり』には、言えば世紀末の匂い、こんなに馬鹿騒ぎをしている喜劇ではあるのですが、そういう匂いを演じるたびに感じるんですね。また一方で、それこそリヒャルト・シュトラウスのような豊満な音楽も同じ時代に満ち溢れていたりする中で、こういうオペレッタが流行っていたのは、やっぱり時代の危うさなのかなというのをすごく感じながらいつも演じておりました。今回の萬斎さんの演出プランを先日伺わせていただいた時にも、やっぱり世紀末的なところから新しい時代が生まれてくるのをフューチャーしながらやりたい、というようなことをおっしゃっていましたし、萬斎さんもオペレッタは初めてだということで、とても挑戦的ですよね。本当に挑まれているという感じがしていますので、それにこちらがどう応えていったらいいのかを楽しみにしているところです。是非よろしくお願い致します。
 幸田浩子 アデーレ役を演じさせていただきます。この『こうもり』という作品は、二幕になると、みんなそれぞれの人が別の人に変装して仮装するんですけれども、そうやっていつもどこかにみんなが持っているような、誰か他の人になってみたい、非日常を生きてみたい、という気持ち。それは、古今東西どこでもあることなんだなと。それこそこの間萬斎さんが、「狂言でも『面』をつける、僕たちも仮面をつけるんです」とおっしゃっていて、仮面舞踏会というものがその時代には流行ったりしましたけれど、仮面をつけて他の人になったからこそ、本人の内側、本質が見えてくる。非日常を経験するからこそ、今の自分の日常をまたもっと愛おしく思えるというようなことをより深く感じながら、お客様ともそこを共感しながら、「こういうことが昔も今も大切なんだよね」を、皆様と一緒に作り上げていけるんじゃないかなと思っています。皆様と共演し共感できることを楽しみにしております。
幸田浩子 アデーレ役を演じさせていただきます。この『こうもり』という作品は、二幕になると、みんなそれぞれの人が別の人に変装して仮装するんですけれども、そうやっていつもどこかにみんなが持っているような、誰か他の人になってみたい、非日常を生きてみたい、という気持ち。それは、古今東西どこでもあることなんだなと。それこそこの間萬斎さんが、「狂言でも『面』をつける、僕たちも仮面をつけるんです」とおっしゃっていて、仮面舞踏会というものがその時代には流行ったりしましたけれど、仮面をつけて他の人になったからこそ、本人の内側、本質が見えてくる。非日常を経験するからこそ、今の自分の日常をまたもっと愛おしく思えるというようなことをより深く感じながら、お客様ともそこを共感しながら、「こういうことが昔も今も大切なんだよね」を、皆様と一緒に作り上げていけるんじゃないかなと思っています。皆様と共演し共感できることを楽しみにしております。
 藤木大地 オルロフスキー公爵を演じさせていただきます。僕はヨーロッパでオペラ歌手になりたくて、オーディションをいっぱい受けるんですけど、オルロフスキー公爵が歌う歌がオーディションのレパートリーだったんですね。ポジションピースで。それでうまくいったオーディションも結構いっぱいあるのですが、なぜかこの役だけは頼まれたことが今までなくて、日本でもなくて、僕は初めてオルロフスキーやります。とても嬉しく思っています。
藤木大地 オルロフスキー公爵を演じさせていただきます。僕はヨーロッパでオペラ歌手になりたくて、オーディションをいっぱい受けるんですけど、オルロフスキー公爵が歌う歌がオーディションのレパートリーだったんですね。ポジションピースで。それでうまくいったオーディションも結構いっぱいあるのですが、なぜかこの役だけは頼まれたことが今までなくて、日本でもなくて、僕は初めてオルロフスキーやります。とても嬉しく思っています。
それで、カウンター・テナーというのは、男性が女性の音域で歌っていると表現をされることがよくあるのですが、僕はもうそろそろそういわなくてもいいじゃないかと思っていて。僕は10年以上カウンター・テナーとして歌っていて、音は高いですけれども、男性が男性の声を使って歌を歌っていることに違いはないんですね。だからこのプロダクションで、カウンターでオルロフスキーを歌うことはもしかしたら珍しいのかもしれないですけれども、そこに注目して欲しくないんです。カウンター・テナーがなんとかというよりも、僕としてはやっぱり、僕が初めてオルロフスキーを歌うことが大事で、一人の人間がオペラを歌って演じるわけなので、それぞれの役の人達がそれぞれの普段の生活を持っていますから、そのひとつだと思っていただけたらと。
とは言うものの、やっぱり『こうもり』という作品のオルロフスキー役はアルト、メゾソプラノのために書かれているので、ほとんどの場合女性が演じるんですね。だから今回阪さんが僕をと言ってくださったこと、僕はずっと阪さんのことをWBCの栗山監督みたいな人だと思っているのですが、その阪さんが藤木を指名してくれたので、僕も大谷翔平にならないといけないかなと思って(笑)、責任を持って歌いたいと思っています。
僕は今日萬斎さんに初めてお会いして、演出のこともはじめて伺ったのですが、基本的にオペラをやる時というのは頭空っぽで、もちろん音楽の準備をするし役柄の準備はするんだけれども、その演出家の方が作る世界にみんなで1ヶ月かけて染まって、同じ舞台を作っていくことがオペラの醍醐味だと僕は思っています。今回もそのように新しい何かに出会えることを楽しみにして、皆さんと劇場でお会いすることを、とても喜ばしく楽しみにしています。劇場でお待ちしています。
【質疑応答】
 ──言語の処理や台本の処理は今回どうなさるんでしょうか?
──言語の処理や台本の処理は今回どうなさるんでしょうか?
阪 言葉に関しては、芝居を日本語にして歌唱をドイツ語で歌います。
野村 僕が一番驚いたのは演出というのが台本も書くんだということで。これは後から聞いて驚いて、今必死になって面白く書こうとしております。
──藤木さん、オルロフスキーをカウンター・テナーが歌うというところに注目してほしくないというお話でしたが、やはりどうしてもこの役柄を女性が歌うというのがこの作品の大きなポイントというか、ひとつの魅力だと思うんですね。その役をカウンター・テナーである藤木さんがどのように捉えてどう歌おうと思っていらっしゃるのかを、お聞かせいただけますか?
藤木 役柄としては、すごく恵まれた人なのに退屈していて満足しいていない、そして偉そうでという、割と僕に似ていると思うんですけど(笑)。でも、満足していないというのは逆の意味で言うと、もっと楽しいことを探している、もっと素敵な環境を目指しているということで、これをポジティブに捉えたいと思います。そういった意味で役柄としては、特に妖精になる時とか英雄になる時よりは簡単です。楽譜があって、それが仮にメゾソプラノで書かれていたとしても、音域として自分が歌えれば僕は歌っていいことにしているんです。それはオペラでなくても、リートでもなんでもです。だからもともと曲が書かれたときの最初のキャストはいるんですけど、現代にそれをやる意味というのは、今その楽譜を見て何を感じるかだと思うので、もう一度繰り返すとそこがカウンターであることは、自分にとっては関係ないですね。
 阪 どうして指名したかというところでもあると思います。今回のキャスティングは一人ずつ僕が全部したので、全て僕の責任です。オルロフスキーは一番難しい役だと思っているんです。とにかく座を締めなきゃなきゃいけないのに、この人がふらふらしていて酔っ払っている。でも酔っ払っている芝居がまた難しくて、何をしゃべっているのかわからないとか、個性をどう出すかを考えたときに、この人のやんちゃな雰囲気がボーンと出ればなと思いました。例えばモーツァルトの『フィガロの結婚』のケルビーノとか、リヒャルト・シュトラウスの『薔薇の騎士』のオクタヴィアンとか、男性の役なのですが女性がやっている、ズボン役と言われるもののちょっとした不思議さは、その時代の産物のような気がするんですね。そして、オペレッタはキャラクターが一番大事なので、楽譜通りというのはどういう意味で楽譜通りかというと、オペレッタに関しては正確さだけでは済まないと思いますから、そこに彼のパンチを期待しています。
阪 どうして指名したかというところでもあると思います。今回のキャスティングは一人ずつ僕が全部したので、全て僕の責任です。オルロフスキーは一番難しい役だと思っているんです。とにかく座を締めなきゃなきゃいけないのに、この人がふらふらしていて酔っ払っている。でも酔っ払っている芝居がまた難しくて、何をしゃべっているのかわからないとか、個性をどう出すかを考えたときに、この人のやんちゃな雰囲気がボーンと出ればなと思いました。例えばモーツァルトの『フィガロの結婚』のケルビーノとか、リヒャルト・シュトラウスの『薔薇の騎士』のオクタヴィアンとか、男性の役なのですが女性がやっている、ズボン役と言われるもののちょっとした不思議さは、その時代の産物のような気がするんですね。そして、オペレッタはキャラクターが一番大事なので、楽譜通りというのはどういう意味で楽譜通りかというと、オペレッタに関しては正確さだけでは済まないと思いますから、そこに彼のパンチを期待しています。
 ──ヨーロッパではオペラの演出は大胆な読み替えというものが主流ですが、びわ湖ホールの前芸術監督は、原典に忠実なオペラを上演されてきたかと思います。今回阪さんが芸術監督に就任され萬斎さんを演出に迎えて、どう新しいものを取り入れていこうとしているのですか?
──ヨーロッパではオペラの演出は大胆な読み替えというものが主流ですが、びわ湖ホールの前芸術監督は、原典に忠実なオペラを上演されてきたかと思います。今回阪さんが芸術監督に就任され萬斎さんを演出に迎えて、どう新しいものを取り入れていこうとしているのですか?
阪 僕はそういう読み替えのものも、また原典に忠実なものも色々とやってきましたが、どちらにせよ良いか悪いかじゃないか?と思っています。もちろん自分が理解できても、お客様が理解できるかどうかというのはまた違う話ですし、どんな読み替えでもなるほど、と納得させてもらいたいというのは、今も昔も同じだと思います。音楽家は楽譜に書いてあることを信用するので、それと違うものが出てきたときに、頭ではわかるけれども腑に落ちていない状態だともやもやしてしまうのですが、例えば良い人が悪い人になっている、だと難しくても、実は知っていてやっていた、というようなことなら近づきやすい。それを読み替えと言うのか言わないのか僕にはわかりませんが、何が正しいか間違っているかではなくて、美味しいか美味しくないかなら人によっても違うので、演出もこれからですから、別にこうでなきゃいけないとは何も考えていません。

野村 結構激烈な演出を考えていて、あんまり言うとちょっとネタバレになるので言いたくない(笑)。でも今会見で皆さんの話を聞いて、ヒントがどんどんインプットされているので、脳みそが活性化されております。シェイクスピア作品にもずいぶん出会っていて、悲劇も喜劇も、それこそチャップリンの名言にもありますけれども、クローズアップするのとロングショットで撮るのとでは人間の映り方が変わるんですよね。
『こうもり』では皆さん色々な思いを持って仮面舞踏会にくるわけですが、その時の皆の心境というのはクローズアップすれば響く、一生懸命な思いでやっているのだけれども、それをちょっと引いてみるとまるで動物園のようだ(笑)、多様な人間がいるなと滑稽に映る。これが私の中での能と狂言の位置で、喜劇だからと言って急に脱ぐとか、そういう飛び道具的な笑いではなくて、どちらかというと一生懸命生きている人間というものに、ちょっと距離感を持ってみたりするとおかしくもなる。でもやっぱり実際の曲に従って歌うことはその人の思いを伝えるものだろうと思います。そういう距離感をいろいろ開いたり、閉じたりする瞬間、まさしくオペレッタにセリフがあるのは、そういうことかなと思うわけです。
能と狂言もそうですけれども、そういった意味での開くという作業を一人、歌い手でない人がやるべきだろうと。そういう意図でキャスティングされているのかなぁとも思いつつ、そこにどういうふうに皆さんが絡んでくるかでまた面白くなるかなと。やっぱり僕自身も古典芸能の中で生きているので、いろいろ時代の制約を飛び越えてクラシカルな世界から飛躍する。突き詰めて細かいことを言っているとつまんないので(笑)。そういうことを軽く飛び越えていくというのがまさに、最後のシャンパンで飛ばしちゃうというところだろうと。
細々答えていると道徳的になっちゃいますし、やっぱりつくづく喜劇の出現性というのは、皆さんの代わりに理性のタガが外れるというところかなと思うんですよ。そういう意味での人間賛歌ということが歌えたらいいなと思っています。それがひとつの演出意図でもありますし、僕は型に押し込めるのではなくて、その方々の個性を自由に生かしたいタイプの演出家ですので、皆さんと色々コミュニケーションをしながらやっていきたいと思っています。

【公演情報】
2023年度 全国共同制作オペラ
J.シュトラウスII世/喜歌劇『こうもり』
ドイツ語上演・日本語台詞 日本語・英語字幕付
指揮:阪哲朗
演出:野村萬斎
出演
アイゼンシュタイン:福井 敬
ロザリンデ:森谷真理
フランク:山下浩司
オルロフスキー公爵:藤木大地
アルフレード:与儀 巧
ファルケ:大西宇宙
アデーレ:幸田浩子
ブリント博士:晴 雅彦
フロッシュ:桂 米團治
イーダ:佐藤寛子 ほか
管弦楽:ザ・オペラ・バンド
●11/19◎滋賀・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
●11/25◎東京・東京芸術劇場コンサートホール
●12/17◎山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館) 大ホール
〈東京公演問い合わせ〉東京芸術劇場ボックスオフィス 0570-010-296 (休館日を除く10:00-19:00)
〈公式サイト〉https://www.geigeki.jp/performance/concert272/
【取材・文・撮影/橘涼香】
Tweet