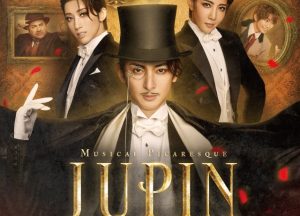紅ゆずるによって蘇る菊田一夫の名作と、星組が紡ぐ星々のレビュー。

宝塚歌劇にその名を残す珠玉の名作として名高い Once upon a time in TAKARAZUKA『霧深きエルベのほとり』と、満天の星空を星組生に例えたスーパー・レビュー『ESTRELLAS(エストレージャス)〜星たち〜』が日比谷の東京宝塚劇場で上演中だ(24日まで)。
『霧深きエルベのほとり』は、日本を代表する劇作家として今もその名を遺す菊田一夫が1963年に宝塚歌劇に書き下ろした作品。初演当時主演を務めた内重のぼるの代表作でもあり、1967年内重退団公演として再演。更に1973年に古城都、1983年に順みつき主演での上演を重ねて以来、30有余年ぶりにOnce upon a time in TAKARAZUKAとして、紅ゆずる主演で宝塚歌劇の舞台に蘇ることになった。

【STORY】
年に1度のビア祭を迎えて浮き立つドイツ北部の港町ハンブルグ。この日寄港した貨物船フランクフルト号から降り立った水夫のカール(紅ゆずる)は、仲間のトビアス(七海ひろき)、マルチン(瀬央ゆりあ)らと共に繰り出した酒場で、1人の娘マルギット(綺咲愛里)と出会う。
家出をしてきたという如何にも世慣れないマルギットと酒場を抜け出し、ビア祭を楽しんだカールは、自由を求めて家出をした娘は、酒場で出会った男に酷い目にあわされるのが相場で、自分がその男になるのは気が進まないと軽口を叩き、一度はマルギットと別れようとするが、一目で惹かれ合っていた二人は、互いに真心さえあれば幸せになれると固く抱き合う。
一方、上流階級の青年フロリアン(礼真琴)は、家を飛び出したマルギットを探していた。実は、マルギットは古都リューネブルクの名門シュラック家の長女で、フロリアンは彼女の許婚だった。自分との結婚を避けてマルギットが家を出たと考えているフロリアンは、懊悩しながらも尚彼女を愛し、そんなフロリアンをマルギットの異母妹シュザンヌ(有沙瞳)は密かに愛していた。
翌朝、エルベ河の畔のホテルで一夜を過ごしたカールとマルギットは、幸福に酔いしれながら結婚の約束を交わすが、マルギットの父ヨゼフ(一樹千尋)の要請を受けてマルギットを捜索していた警察に、カールは誘拐の容疑をかけられ、警官たちの手で二人は引き裂かれかかる。だが、父と実母との間にあった確執に対する葛藤を心に抱えていたマルギットは、自分が家を出た理由はヨゼフが1番知っている。自分にはカールと結婚するか死ぬかどちらかしか選択肢はないと言い放ち、ナイフを我が身に押し当てる。
その場を収めたフロリアンのとりなしで、カールはマルギットの婿養子としてシュラック家に迎えられるが、上流階級の人々がカールを見下す視線は冷たく、二人の住む世界の違いがマルギットの心に惑いを生じさせていくのを敏感に察知したカールは、愛するマルギットの為に自分が取るべき行動を思いあぐねていき……

30数年ぶりにこの作品に接して改めて思うことは、身分の違う男女が出会い、愛し合い、結婚の約束を交わすものの、互いの育った環境の違いの大きさの前に、二人は運命を違えていく、という、言ってしまえばただそれのみのストーリーで、1時間半の作品が出来上がっていることへの畏怖の念だ。あるのはただひたすらに二人の短くも激しく燃え上がった切ない恋模様だけで、登場人物たちの感情の移り変わり、心の機微を精緻に描き込むことに90分が費やされる。こんな徹頭徹尾のメロドラマを、現代の作家に書いて欲しいと願ったとしたら、むしろ手も足も出ないのではないか。そんな想像をしてしまうほど、この作品の底力には類を見ないものがあり、何を今更と言われることだろうが、天才劇作家・菊田一夫の筆の見事さにはただ舌を巻く思いがする。
しかも瞠目すべきは、この作品が実のところ、ヒロインのマルギットにとってのみ都合の良いストーリーとして運ばれている点だ。人も羨む名家の長女に生まれ、同じ上流の申し分ないどころか、性格が良いにもほどがある紳士の許婚に愛されながら、父親と実母の別れに疑念を抱いて家を飛び出し、粗野だが心根が優しく人情にも篤い海の男と恋に落ちる。けれどもその行動故に両親の確執の真実を知って、父親に抱いていたわだかまりも解けた彼女の為だけを思い、海の男は潔く身を引き、変わらずに傍にいてくれる、自分がいるべき世界に相応しい許婚とおそらく結婚して尚、この世界のどこかでずっと自分愛し続けてくれている男がいるという、美しい恋の思い出が心の宝箱にずっと残る……
こう書いて改めて驚くほど、この物語はヒロイン無双にできていて、ヒーローに対してあんまりじゃないか、可哀想すぎるじゃないか、と、ついついヒーローの心情に加担してしまうことまでも含めた全てが、菊田一夫の綿密な作劇故なのだろう。良家の子女が安心して(決して自分は傷つかず)ヒロインに理想の恋を仮託できる世界こそが、1963年初演当時の宝塚歌劇の正義で、それ故にこの大メロドラマは傑作として宝塚歌劇に残った。
そんな宝塚歌劇が100周年を迎え、次の世紀への歩みを進める2019年現在までの間に、男性が絶対優位な社会の不平等と戦い、自分に与えられていた特権の全てを捨てて革命に身を投じていくオスカルを中心とした『ベルサイユのばら』が金字塔を打ち立て、更に自らが求める魂の自由の為ならば、果たすべき義務も放棄し、どんな批判も歯牙にもかけず己の心のままに突き進むエリザベート皇后をヒロインとした『エリザベート』が新たな代表作となっていることを思うと、改めて隔世の感があるし、その新しい時代の申し子とも言える世代の劇作家上田久美子が、この類稀なるメロドラマのどこに心酔したのかにも、計り知れないものがある。けれども、こうしたただひたすらに恋愛1本勝負の作品に、上田が正面から取り組めたことには間違いなく多大な意義があるし、深く濃く描かれた登場人物たちの感情の襞と向き合った星組の面々にも、この経験は大きな糧になるに違いない。

その筆頭がカールに扮した紅ゆずるで、コメディエンヌとしての頭抜けた才能とサービス精神を封印して、実際にはきっといないだろう恋に一途な、愛した者にのみ真心を注ぐ男の中の男をじっくりと演じた紅が獲得した、男役としての大きさに感嘆する。マルギットとの恋に軽口を言いながら踏み出すことをためらったのには、カールの中にかつてなくした恋の傷という原因があり、その相手であるアンゼリカ(音波みのり)が何故自分を選ぶことができなかったのか、その事情も全てわかって、後悔しなくてよい、「旦那に可愛がってもらえ」と背中を押してやる。しかも結局新たに踏み出した恋でももっと深く傷つくのに、思うのはただ相手の幸せだけ。こんな男性像に少しも嘘臭さを感じさせずに、90分の間本当にいると思わせた紅の男役芸に拍手を贈りたい。惜しくも次公演での退団を発表している紅が、ここでカール・シュナイダーに出会えたこと、そのものを喜びたい仕上がりだった。

ヒロイン・マルギットの綺咲愛里は、前述したようにあまりにも全てがヒロインに都合よく展開されるストーリーを、尚もっともだと思わせるひたすらな可憐さで、現代の目から見てもこの令嬢を鼻持ちならない女性に見せなかったのが素晴らしい。実際この役柄を現代の娘役が、現代の観客に共感の念を持って見てもらうのには、想像以上に高いハードルがあったと思うが、存在自体が作り込まれた人形のようですらある綺咲の愛らしさが、そのハードルを越えるのに役立っていて、最後まで紅と共に歩むと発表している綺咲のキャリアにとっても、マルギットは貴重なものになった。
マルギットの婚約者フロリアンの礼真琴は、初演当時はとても美味しい台詞の多い、純二枚目と解釈されていただろう役柄を、少ない動きの中で懸命に描き出した労を称えたい。やはりこの紳士も現代の目で見ると、正しいことしか言わない、どこか息苦しい青年像に写り兼ねないところに、奇をてらわず真摯に向き合った日々は、歌とダンスに秀でた活きの良い男役である礼真琴の進む道に、必ず貴重な時間になったと思う。切ない心情を訴えたソロも豊かに聞かせた。
そんなフロリアンを密かに愛するマルギットの異母妹シュザンヌの有沙瞳も、よく書き込まれた役柄に持ち前の実力が加味され、切ない恋心と、このシチュエーションだと多少なりマルギットに反感を抱いても不思議ではないシュザンヌが、尚、姉のことを案じている心情をよく表現している。また、主人公カールの男ぶりをより引き立たせる重要な鍵になる元恋人のアンゼリカの音波みのりの、美しさ、健気さが役割を見事に果たしていて、この公演の後に控える礼主演の全国ツアー『アルジェの男』で、ヒロイン・サビーヌ役が彼女に配されたことも、当然と思わせる娘役ぶりが健在。こうした組を豊かにする人材の労が報われることが嬉しい。他にもカールが唯一真実を打ち明ける相手になる、専科の英真なおきが母性豊かに演じた酒場の女ヴェロニカや、如何にも新進娘役に相応しい役柄を、水乃ゆりが快活に演じたカールの妹ベティなど、女性の役どころがよく書き込まれているのも作品に彩りを与えている。

その一方で、男性の役柄はどちらかと言うとグループ芝居の傾向があるが、カールの船乗り仲間としてマルチンの瀬央ゆりあが、思いを素直に口にする裏表のない海の男を描けば、ワンテンポ、ツーテンポ周りからズレているのに全く憎めないオリバーを、麻央侑希がのほほんと演じるのが実にこの人らしいし、カールに手持ちの金を巻き上げられてばかりの人の好いエンリコを紫藤りゅうが爽やかに演じる等、それぞれの個性を立たせているのも頼もしい。マルギットの父ヨゼフの専科の一樹千尋の重みはもちろん、警部のカウフマンの天寿光希もいぶし銀の味わいを醸し出している。
そうした男役たちの中で、カールの妹のベティと恋に落ち、船を降りて新たな世界に旅だっていくトビアスに七海ひろきが扮して、特段の印象を残している。星組の豊かさの象徴だったこの人が、このタイミングで退団という道を選んだことには、様々な思いが去来する。どこにいても目を引く美貌で、おおらかで、どんな役柄にもちゃんと背景を感じさせるだけでなく、七海ひろきが演じるからこその温かさも加えてきた、ここまで大きな存在になった男役の花道に別の形はなかったものか、せめてもサヨナラショーなりが用意できなかったものかと、観客として悔いが残らなかったと言ったら嘘になる。それでも新天地に向けて「あばよ!」と鮮やかに去っていくトビアスの残す光彩が、七海のそれと重なってただ幸せにと祈る気持ちが自然に劇中に膨らんだことを、今は多としたい。扉を開けて去っていくあの残像は、長く宝塚に残ることだろう。

そんな宝塚歌劇のなんたるかを知らしめた名作の再演のあとに、星組の多彩な陣容を星々に例えたレビュー『ESTRELLAS〜星たち〜』があることも、公演としての座りを格段に良くしている。基本的に作者の中村暁が創り出す定番中の定番に則った場面構成だし、J-POPやK-POPをふんだんに盛り込んだ楽曲選びにも新味はないが、だからこその安定感があって、宝塚歌劇の定番フルコースを堪能した気持ちにさせてくれる。芝居が古典と言っていいものなだけに、あまりエッジなショーはバランス感を欠く恐れがあり、結果として良い組合わせになった。客席降りもふんだんにあり、観客のボルテージが自然にあがることも良い。

中でも紅と綺咲のコンビぶりに磨きがかかって、二人の様々な表情が楽しめるし、デュエットダンスの幸福感は、芝居が悲恋で終わったことを昇華するかのよう。K-POPでは礼の抜群の歌声と共に、胸のすくダンスが見応えたっぷり。瀬央の存在感がグンと上がり、麻央、紫藤、天華えま、極美慎の躍進ぶりも際立ち、フィナーレまで飽きさせない。エトワールの華鳥礼良の歌声が美しいだけに、貴重な歌姫の早い退団が惜しまれる。

そして七海に大きな場面が任されていることが、惜別の餞として何よりも嬉しく、明るいイエローの衣装と共にキラキラ感がさく裂。『ESTRELLAS〜星たち〜』のタイトルに相応しい、星組スターたちの輝きに満ちたレビューとなっている。


また、初日を前に囲み取材が行われ、星組トップコンビ紅ゆずると綺咲愛里が記者の質問に答えて公演への抱負を語った。

その中で名作の再演である『霧深きエルベのほとり』に取り組んだ心境を訊かれた紅が、時代背景や価値観が現代とは全く違う作品で、その時代の水夫が感じていた幸せとは何かを知って、今の時代に新たなものを生み出す気持ちでいる、という非常に深い趣旨の発言で、作品の核心をつく。

綺咲も、名作に携われることを光栄に思い、今の時代のお客様にも共感して頂ける舞台づくりをしたい、とやはり大切な視点をもって作品に向かっていることを感じさせた。

更に、華やかなショーでのお気に入りシーンは、二人共に即答で「デュエットダンス」とのことで、ダンス自体が芝居の要素が濃いことから、芝居の延長のような気持ちでやっているという言葉があり、紅が幸福感に満ちた表情で綺咲を迎えるデュエットダンスの真髄を感じさせ、退団を発表したことは今は意識せずに、この公演に集中したいという二人の姿勢が現われる時間となっていた。

尚、囲み取材の詳細は、舞台写真の別カットと共に5月9日発売の「えんぶ」6月号にも掲載致します!どうぞお楽しみに!
【公演情報】
宝塚星組公演
Once upon a time in TAKARAZUKA『霧深きエルベのほとり』
作◇菊田一夫
潤色・演出◇上田久美子
スーパー・レビュー『ESTRELLAS(エストレージャス)〜星たち〜』
作・演出◇中村暁
出演◇紅ゆずる 綺咲愛里 ほか星組
●2/15〜3/24◎東京宝塚劇場
〈料金〉SS席 12,000円 S席 8,800円 A席 5,500円 B席 3,500円 (全席指定・税込)
〈お問い合わせ〉東京宝塚劇場 03-5251-2001
【取材・文/橘涼香 撮影/岩村美佳】
Tweet