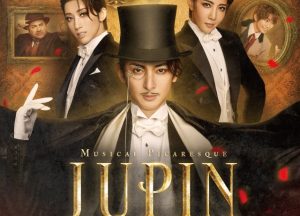大人気ミステリーの華麗なる宝塚化!宝塚花組『マスカレード・ホテル』

宝塚歌劇団花組の男役スターとして活躍する瀬戸かずや主演による、宝塚花組公演ミステリアス・ロマン『マスカレード・ホテル』が日本青年館で上演中だ(27日まで)。
ミステリアス・ロマン『マスカレード・ホテル』は、日本の誇るミステリー作家の第一人者・東野圭吾の、シリーズ累計発行部数360万部超の大ヒット作品「マスカレードシリーズ」の第一作目を原作に、宝塚歌劇が初めて舞台化した作品。2019年1月には木村拓哉、長澤まさみ主演で映画化され、こちらも大ヒットを記録している人気作品に、宝塚歌劇が挑む意欲作となっている。
【STORY】
都内で次々に起きた殺人事件。一つひとつの事件には一見関連性がないように思われたが、警察は連続殺人事件として秘密裡に捜査を進めていた。というのも、それぞれの事件現場に残されていた暗号が、次の事件の場所を予告するものになっていることが突き止められたのだ。この解読から警察は、次に起こるだろう犯行現場を都内でも有数の一流ホテル「ホテル・コルテシア東京」であると推測し、潜入捜査を断行。それは、刑事たちがホテルの従業員にそれぞれ扮し、新たな殺人事件を未然に防ごうという計画だった。中でも重要なフロントクラークに扮するよう命じられたのが、警視庁捜査一課の刑事・新田浩介(瀬戸かずや)。帰国子女で語学に堪能な新田以外に、この重責を務められるものはいないと白羽の矢が立ったのだ。だが、刑事が簡単にホテルマンに化けられるはずもなく、新田の指導を任されたホテルのフロントクラーク山岸尚美(朝月希和)は、風貌も言動もおよそホテルマンらしからぬ新田がフロントに立つ為には、ホテルマンの心得の全てを体得してからでなくてはダメだと、厳しい特訓を開始する。一日も早くフロントに立ち犯人の目星を付けることに気が逸る新田は、一挙手一投足に口を出す尚美と衝突を繰り返すが、ホテルマンとしての誇りを持ち、やってくる様々な客たちの、無理難題も含めた要望に笑顔で対処し続ける尚美に次第に一目置くようになっていく。尚美もまた、新田の鋭い勘や機転に助けられ、犯罪を未然に防ごうとする新田の、刑事という職業に懸ける思いに共鳴していく。
そうするうちにもホテルには、次々と新たな宿泊客が現れ、度々騒動が巻き起こる。「ホテルにくるお客様はみんな仮面をつけていらっしゃる。我々はその仮面を決して剥がしてはならないのです」という藤木総支配人(汝鳥伶)の言葉が重く響く中、その仮面の下の犯人の素顔を求めて新田は奮闘を続けるが……

ミステリーの醍醐味の王道はなんと言っても犯人捜しにあって、読書の楽しみには作家が仕掛けた様々なブラフやミスリードをかいくぐって、如何に真犯人を看破するか?という点が大きい。この作家VS読者の対決を公平なものにする為に、「犯人は物語の当初に登場していなくてはならない」「探偵方法に超自然能力を用いてはならない」をはじめとした、推理小説を書く上でのルールを定めた「ノックスの十戒」や「ヴァン・ダインの二十則」などが知られているほどで、作家もルールを破らずに謎を仕掛け、読者も正々堂々とその謎に挑むという謎解きの楽しみは、ミステリーに欠かせないものだ。
ただ一方で、これらの著名な法則を敢えて破って、ミステリーの枠を広げようとする試みや、推理小説を犯人捜しのエンターティメントから、更に文学へと押し上げようとする作品も数多く書かれているし、端的に言って最も良い推理小説は、再読に耐えるものというのも定説だ。つまり犯人を知ってからでも、逆に作家がどんなミスリードを仕掛けていたかとか、張られていた伏線を反芻しながら読むことのできる推理小説には、登場人物の心理描写をはじめとした、奥深い興趣があって飽きさせない。
そういった一級のミステリーを書くことに於いて定評があり、更に非常に多くのテイストの作品を書き分けている東野圭吾の作品の中でも、エンターティメント色が濃く、露出も多い「マスカレード・ホテル」を宝塚が舞台化するにあたって、作品の主眼を犯人捜しではなく、ヒーローの刑事とヒロインのホテルのフロントクラークが、本来生涯出会うはずのなかった運命の出会いから、心を寄せていくまでの展開に置いた脚本・演出の谷正純の目線は、極めて正しいものだったと思う。何しろ原作はもちろんだが、映画版があまりにも知られている作品だけに、こと宝塚の場合にはキャスティング発表以前の、この作品に出演するメンバーが発表された段階で、犯人役はこの人だな…と読めてしまったほど。その為、事件捜査の部分を決して無視した訳ではないながら、ポイント、ポイントの要約説明といった趣に留めて、人間模様の描写に時間が割かれていたのが、作品を宝塚の舞台で自然に演じられるものにしていた。基本的には「この人が犯人かも?」の為に、さまざまに現れる訳アリの登場人物たちの存在も、多くの出演者に役をつけたい宝塚歌劇にとっては効果的に作用していて、これは思わぬ発見。特にタイトルの「マスカレード・ホテル」、ホテルには人がひと時仮面をつけて、非日常を味わう為にやってくる、という説明から幻想の仮面舞踏会に発展していく流れが非常に美しく、宝塚にとっては十八番と言っても過言ではない場面だけに、宝塚ここにあり!の魅力が噴出する。この展開を1幕のクライマックスに持ってきた、ベテラン作家谷正純の仕事ぶりが取り分け光った。芝居の楽曲をすべて手掛けた作曲家植田浩徳の作風にも、良い意味の懐かしさがあり、初めて観る作品なのに、この主題歌を聞いたことがある気がする…と思ったほど、宝塚歌劇の世界観に楽曲がすんなりと馴染んでいるのも心地良かった。

そんな挑戦の作品でありながら、安定感のある舞台で主演を務めた瀬戸かずやが、長年培ってきた男役芸を存分に披露している。花組の前任トップスター明日海りおの時代から、ニヒルで大人の男の風情が濃い個性で重用されてきた瀬戸だが、ある時期まで決して器用な人ではないなという印象が強かったところが『蘭陵王』で、生まれた性と性自認が異なる難しい役柄を体当たりで演じて以来、大きく殻を破って舞台姿に俄然余裕が出てきた。こうなると元々の男役度の高さが更に強い武器になってきて、ホテルのフロントクラークに完璧に化けているように見えて、目付きはちゃんと刑事というキャラクターが、瀬戸の持ち味にピッタリ。態度は斜に構えていても、仕事に対して真摯で誠実という新田の根本もよく表現されていて、見どころの多い主演ぶりだった。新トップスターの柚香光に溌剌とした少年性があるだけに、この人の大人の男役は、新生花組でも貴重な戦力になることだろう。
一方ヒロインの朝月希和は、花組から雪組に組替えして、彩風咲奈のダンスパートナーを多く務めるなど、大活躍をしたのちに、再び花組に戻りヒロインの座を射止めた。明日海退団時に有望な娘役が同時退団していた花組の事情もあっての人事だっただろうが、その里帰りに納得がいく、あくまでも仕事に誇りを持ち、困難も悩みもすべて笑顔の下に包み込む矜持を持った女性像を的確に演じている。何よりも役柄の格になる「笑顔」がなんとも愛らしいのが朝月の魅力で、ヒロイン尚美役に打ってつけ。これは想像を遥かに超える好演で、「花娘」としての今後の活躍が更に楽しみになった。
この二人の関係が、原作とも映画とも異なるときめきのあるエンディングを迎えるのも、シリーズ化を見据えているのだろう他メディアとの違いを浮き彫りにし、宝塚ならではのラブロマンスの良さにつながったのも美しかった。

また、新田の相棒になる能勢金治郎の設定を原作から変更し、新田の後輩にした中での様々な工夫も面白く、飛龍つかさが真面目さとちゃっかりさを上手くブレンドして、作品の良いアクセントになっている。出番が比較的飛んでいる中でも、この人誰だっけ?にならない存在感を飛龍が備えているからこそ成立している部分も大きく、男役として着実に頼もしさを増しているのが見てとれた。
また、ベル・キャプテン杉下の帆純まひろは、飛龍とは逆に出番の多さに比して、働き場が意外に少ないが、その中でも帆純が演じることによって、役柄が大きく見える効果があることに男役・帆純の成長を感じる。長倉麻貴の音くり寿は、持ち前の歌唱力はもちろん、このところ更に磨きがかかってきた演技力が全開。ますます組での重要度が増しそうだ。ホテルの総支配人・藤木の汝鳥伶の押し出しは言わずもがなだが、それに対する警察側の稲垣係長の和海しょうが、きっちりと新田の上司を務めているのが目を引いた。

他にも前述したように、警察の面々、またホテルの訳アリの客たちで多くの役柄があり、花組メンバーの個性がよく見えた中で、やはり組長の高翔みず希が演じた栗原健治の造形が光る。新田に執拗にクレームを出す役柄で、いくらお客様だからと言ってこれを全て通すのはいくらなんでもゴネ得に過ぎるのではないか、と思わせるキャラクターを高翔らしい品の良さでやり過ぎなかった、その塩梅が絶妙で作品の爽やかさを高めていた。この公演から副組長に就任した冴月瑠那の、フロント・マネージャー久我の誠実さも冴月の個性をよく表していて、作品とは独立した形で途切れなく続くフィナーレも美しく流れ、宝塚ならではの『マスカレード・ホテル』が生み出されたことを喜びたい舞台になっている。
〈公演情報〉
宝塚花組公演
ミステリアス・ロマン『マスカレード・ホテル』
原作◇東野圭吾「マスカレード・ホテル」(集英社文庫刊)
脚本・演出◇谷正純
出演◇瀬戸かずや ほか花組
●1/20~27◎日本青年館ホール
〈料金〉S席 8,300円 A席 5,000円 (全席指定・税込)
〈お問い合わせ〉宝塚歌劇インフォシメーションセンター[東京宝塚劇場]0570-00-5100
公式ホームページ http://kageki.hankyu.co.jp/
【取材・文・撮影/橘涼香】
Tweet