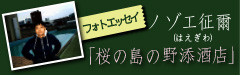【一十口裏の「妄想危機一髪」】第71回 キュート

頼んでいた本が届いたのかと思った。
まだ寝ぼけていた私はチャイムが鳴るのを無視したが、
玄関を開ける音がして、母の声の次に知らない男の声がしたので、
急いでズボンを履き替えて、二階から駆け降りた。
するとやはり宅配便の男が、荷物を母に手渡していた。
しかし男は荷物を手渡すと両手で猫のポーズを取り、猫のように鳴き始めた。
しきりに体をくねらせて、ゴロゴロと喉を鳴らす真似までした。
その男の喉を母は甲高い猫撫で声を挙げて、優しく優しく撫で回した。
私は階段の途中でそれを見た。
ひとしきり男を撫でた母は満足すると、「有難う、ご苦労様」と言った。
ひとしきり母に撫でられた男は、「それじゃ、失礼します」と言った。
言って男は、母の手から荷物を取って、そのまま去って行ってしまった。
私はようやく階段を降りきって、男の去った方を見たまま、こう言ってみた。
「私の本は?」
「え?」
「今の荷物、私の本じゃなかったの?」
「やだ。今のは私に可愛さを届けてくれたのよ」
そう笑う母の頰は紅潮し、目尻と口端が緩みきっていた。
こんな母の顔を、私はこれまで見た事がなかったように思う。
「ふうん……」
そのまま、その先なにも言わぬ母に、私はそう言うしかなかった。
その日、私は久々に家を出た。
久々に履くスニーカーだったが、ズルズルに草臥れているので、
まるで靴下のまま外に出るような感覚だ。
「ほんとにあんたは、可愛げがないんだから…」
子供の頃からずっと言われ続けて来たその言葉には、今さら何の感情も起きない。
可愛げ可愛げ可愛げ。それが何だと言うんだろう。
そんなものは何の役にも立たない。
「駄目なのよ、誰にでも可愛がられるようにならないと…」
しかしそう言う母の眉のシワには、吐き気を催させる作用がある。
本当に私を心配しているような様子で、母はそう言い続けた。
しかし本当に必要なのは別なものであろうと、私は思った。
だから私は汚いシャツとジーンズを着て、髪もとかさなかった。
「だってあんたそんなんじゃ、この先、絶対に困るわよ…」
いくら無視しても、尚そう言い続ける母を黙らせるために、
私はやがて、何をするか分からなくなった。
母の眉の皺は一層深くなり、私の吐き気は止まらなくなった。
早く自立し、早く一人で充分にやっていけるようになりたかった。
だから母の顔を思わず殴りそうになる、その力を、そのために全部使った。
昼夜を問わず、脇目も振らず、誰よりも勉強した。
顔を上げず、ひたすら勉強し、誰よりも良い成績で大学を出た。
なのに就職先は決まらなかった。いくら頑張っても無駄だった。
一般職も専門職も決まらず、研究を続けさせてくれる所もなかった。
しかし更に深まるだろうと思った母の眉の皺は、
そら見たことかと、少しずつ伸びていった。
そのまま額をはみ出ていくんじゃないかと思うほど、伸びていった。
街を歩くのは久々だったし、街で立ち止まったのも久々だった。
今朝のあれは何だったのだろう。私の本はいつ届くだろう。
そう思って久々に顔を上げてみれば、街はすっかり可愛らしくなっていた。
頭上に広がる空の色はパステルカラー。
そこに浮かぶ無数の雲はファンシー。
全てのビルの壁面は甘い香りのクッキーやビスケット。
それらをハート形や星形の看板や広告がきれいにラッピングしていた。
そしてそこを行き交う人々は皆、愛嬌のある笑みを口元に受かべていた。
皆が皆、頭に大きなリボンを乗せて、上目遣いでちょこまかと歩いた。
老いも若きも男も女も、目が合えば、おどけたように眉を上げ、
小首を傾げたり、頰を緩ませたり、唇とを尖らせた。
可愛い。何もかもが、可愛い。
私は慌てて辺りを見渡し、見慣れたコンビニを見つけると、
逃げるようにそこに走り込んだ。
「っらっさっせー」
レジで俯いたままそう言うバイト店員に安心し店内の奥まで走った私は、
ペットボトルのお茶を掴んでレジの上に放り投げるように置いた。
「あ、128キュートになります」
「?」
「あ、128キュートです」
なんだか分からず隣のレジを見ると、
パステルオレンジのニッカポッカを履いたおじさんが、
頭のリボンを揺らして内股に片足を上げ、店員に投げキッスをしていた。
「6キュートのお返しです」
投げキッスをされた店員はそう言うと、
両手を頰に当て頰を赤らめて、おじさんにウインクした。
そうしておじさんはガーリックチキン弁当を持って店を出た。
「キュート…?」
「あ、今年度から通貨単位が変わりました。円から、キュートに」
私が呟くと、私の前の店員はそう言った。
そう言って、じっと私を見つめ、私の128キュートを待った。
私は1キュートも持っていない。
なんだかよく分からないが、
私は店員に渡せるキュートを、1キュートも持っていない。
無言のまま、店内に走り込んだ勢い同様に店外に走り出た私は、
乱暴者だった幼馴染の臼田とぶつかった。
その巨体は間違いなく臼田だった。
しかし臼田はその逞しい体を、細身のスーツにピチピチに包んでいた。
しかし私はそれよりも、繊細なフリルをあしらった、彼の頭上のリボンを見た。
「あれ?菊池、お前、どうしたの?」
「どうも、してない、けど」
「だいじょうぶ?」
そして私は次に、パステルピンクのファンシーなスーツケースを見た。
「臼田は、何してんの?」
「あ、営業で外回り」
「何、売ってんの?」
「もちろん媚びだよ」
「媚び」
聞けば日本の媚びの輸出量は現在世界第3位で、
ほぼそれだけで持っているような状態だという。
世界市場はハグとキスで溢れかえり、各国首脳はキュートさを競い、
紛争地域ではお菓子作りの煙があちこちであがり続け、
テロリストは日々、自撮り写真を加工しているという。
どういうことかと思いつつ横を見れば、
デコレーションケーキのように積み上げられた色とりどりのテレビの中で、
にやけた顔の首相がこれでもかと、媚びを売っていた。
だから菊池も頑張って媚びを売るしかないよと、臼田はキュートに笑って言った。
そうして臼田は私に向かって、ピチピチスーツのお尻をキュッと上げて、
200キュートを貸してくれた。
いつの間にこんなことになっていたのだろう。
いつからこうだったのだろう。
私は200キュートを返せるだろうか。
私はポケットからスマホを取り出し本をキャンセルすると、家に向かって引き返した。
その私の顔には、何の感情も浮かばなかった。
母の眉の皺のように、それはどこまでも間延びしていった。
体中の力が抜けて、フワフワと雲の上を歩くようだった。

 【著者プロフィール】
【著者プロフィール】
一十口裏
いとぐちうら○ 「げんこつ団」団長
げんこつ団においては、脚本、演出のみならず、映像、音響、チラシデザインも担当。
意外性に満ちた脚本と痛烈な風刺、容赦ない馬鹿馬鹿しさが特徴。
また活動開始当初より映像をふんだんに盛り込んだ作品を作っており、現在は映像作家としても活動中。
げんこつ団公式サイト
http://genkotu-dan.official.jp/
▼▼▼今回より前の連載はこちらよりご覧ください。▼▼▼
Tweet